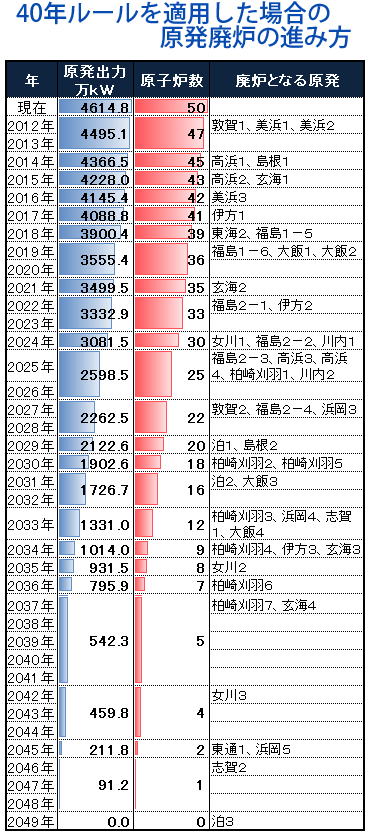3・11東日本大震災と福島第1原発事故を受けて、公明党のエネルギー政策の基本は、以下の3点の集約されます。
3・11東日本大震災と福島第1原発事故を受けて、公明党のエネルギー政策の基本は、以下の3点の集約されます。
- 原発の新規着工は認めない
- 1年でも早い「原発ゼロ社会」実現のため、省エネ・再エネ・ムダのない火力発電に最大限の力を注ぐ
- 原発再稼動は国民が納得・信頼できる確かな安全基準が出来るまでは許さない
原発事故から1年7カ月が過ぎようとする今現在でも、民主党政権のエネルギー政策は迷走を極めています。2030年代に原発ゼロを目指すといっておきながら、核燃料サイクル事業は放棄しないといい、その延長上にある大間原発の建設再開を許してしまいました。東海第2発電所など老朽化し、40年の稼動制限ぎりぎりの原発も、安全対策という名の下に何十億円という資金が投下され続けています。再稼動の判定は誰の責任で行うのか、その基本中の基本も決まっていません。
こうした状況の下、「原発ゼロ社会を目指す」公明党の立ち位置を、井手よしひろ県議の個人的な見解ですが、再度確認してみたいと思います。今回は、なぜ原発ゼロなのかについて述べてみたいと思います。(写真は、東海第2原発の燃料プールを視察した茨城県議会公明党議員団と東海村議団)
原発の新規着工は認めない。原則40年で廃炉とする
原子力発電には2つの危険性が潜んでいます。
第一は、福島第1原発で顕在化した、人知は計り知れない事故の危険性とそれによる放射性物質の拡散という危険性です。福島では16万人が避難を余儀なくされ、放出された放射性物質の人体や動植物への影響に日本人は数十年単位で恐れおののかなくてはなりません(または、実際に深刻な影響が今後起きてくる可能性は、誰人も否定できません)。原子力は危険性の高いエネルギー源であるといわざるを得ません。こうしたリスクのある原発は一刻も早く閉じるべきです。
第二は、使用済み核燃料の最終的な処分「バックエンド問題」です。日本は、使用済み核燃料を再利用するリサイクル方式を現在選択しています。アメリカや中国などの原発大国は、一回使用すれば廃棄するワンスルー方式で、核燃料の最終処分を進めてきます。いずれも、最終的には地層深くに埋設して処分することです。しかし、地層深く埋めたとしても放射性物質の放出がなくなるまで1万年単位の年数がかかると計算されています。全世界で、この問題に一定の結論を得たのはフィンランド(オンカロ)とスウェーデン(フォルスマルク)の2箇所のみです。福島原発事故では、低レベルの放射性物質の処分や瓦礫処理に対しても、地域住民から大きな反対の声が巻き起こりました。日本国内で、原発から出た高レベルの使用済燃料をどの地域が受け入れてくれるのか、その実現性は極めてゼロに近いといわざるを得ません。今まで、日本はこの問題を騙しだまししながら、結論を先送りしてきました。もう結論の先送りはできません。結論として、バックエンド問題を根本的に解決することが困難であるならば、原子力発電は止めるべきです。
原子力発電の存在は認めることは出来ません。しかしその存在は、人間社会にとって大きな役割がありました。20世紀後半の石油ショックから21世紀前半にかけて人類の進歩に貢献したことは、否定できない事実です。
しかし、危険性の高い、バックエンド問題を解決できない原発は、人類史上「一定期間に大きな役割を果たした過渡的エネルギー」と、認識する必要があります。
というわけで、今後、日本では新たな原子力発電所を建設してはならないのです。原子炉規制法で定められた稼働後40年で廃炉という原則通りに、現有する50基の廃炉を進めていくべきです。
建設中の原発をどうするかについても、私見を述べさせていただきます。建設中の島根3号機は、すでに90%以上できています。最新鋭の島根3号機は、他の50基ある原発と比べて最も安全性が高いといわれています。周囲には15mの津波に耐える防潮堤が整備されており、電源喪失時の冷却水確保装置なども完備しています。古い原発を安全性の高い原発に置き換えていくのが得策ではないでしょうか。
一方、大間原発は40%の進捗率です。この原発は、日本初のフルNOX燃料を使用します。プルトニウムの含有量が高いリサイクル燃料を使用し、危険性の高い原発であることも事実です。バックエンド問題が解決困難であることを考慮すると、この炉の建設は断念するのが得策ではないでしょうか。
二者択一を超えて現実的解決を
使用積み燃料の最終処分問題が決まらない問題(バックエンド問題)から原発は、「トイレのないマンション」だといわれ続けました。なぜ、トイレがないマンションを作ってしまったのか、それは、トイレがなくてもいいから家を建てる必要があったということです。日本経済を発展させるためには、その原動力である良質の“電力”を潤沢に提供する必要があったのです。
日本のネルギー政策を考えていく際に重要な視点は、「反対」vs「推進」、「廃炉」vs「再稼動」という二者択一ではなく、危険性と必要性の両面を冷静に直視し、現実的な答えを求めることに努力すべきです。今、原発反対、再稼動反対のうねりの中で、原発反対派が勢いを得ています。反面、産業界・経済界を中心として「日本の国際競争力を維持するためにも、速やかに原発の再稼動を」との圧力も増しています。原発ゼロの道筋をつくるためには、具体的で影響を受ける人々にも受け入れられる議論が必要です。
そこで重要なのは、再生可能エネルギーの開発スピード、省エネルギーの進展度合い、石炭火力やLPGガスで排出されるCO2の影響、こうしたものの総合計から、削減できる原発の発電量を決めていくという発想が必要だと思います。さらに、原子力発電所が立地する地域の産業構造を、どのように変えて地域の活力を維持するかという視点も不可欠になります。
原発ソフトランディングのシナリオを、“二者択一”の議論を超えてスタートさせるべきです。
このように考えると、民主党がいうような2030年代で原発ゼロは、非常の困難な選択肢であるように思われます。公明党が、「1年でも早い原発ゼロ……」と重点政策に謳ったのも、こうした背景があります。