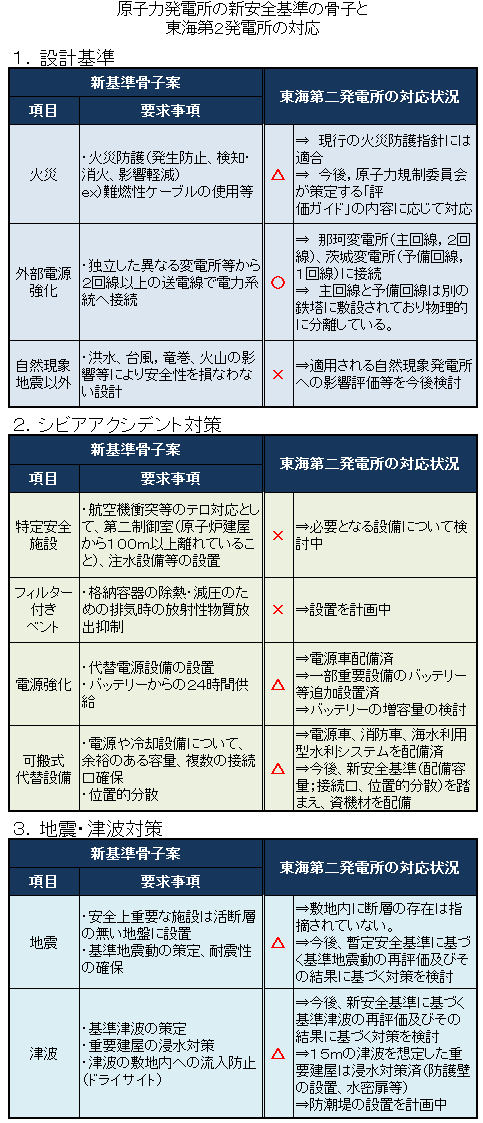3月12日、県議会防災環境商工委員会の生活環境部所管事項の審査が行われ、井手よしひろ県議は東海第2発電所の再稼働問題や不法投棄の撲滅策などについて質問しました。
3月12日、県議会防災環境商工委員会の生活環境部所管事項の審査が行われ、井手よしひろ県議は東海第2発電所の再稼働問題や不法投棄の撲滅策などについて質問しました。
東海第2発電所の再稼働については、「再稼働を容認する立場ではない」と明言した後、国の原子力規制委員会が7月までに策定するとしている新たな安全基準について、東海第2発電所の対応状況を質しました。
東京電力福島第1原発事故を受け、日本原子力発電(原電)東海第2発電所は、当面の安全対策を3月1日までに完了させました。今回完了した対策は、地震・津波、浸水防止、電源確保、注水冷却機能の確保などです。地震・津波対策は海水ポンプ室の防護壁のかさ上げや配管補強を施し、浸水防止対策は原子炉建屋大物搬入口に水密扉を備え、非常用ディーゼル発電機の給排気設備を守る高さ8メートルの防護壁を設置しました。電源確保対策は低圧電源車4台と大容量高圧電源車5台により、非常用ディーゼル発電機のバックアップ機能を整備しました。飛散したがれきなどの撤去用のブルドーザ2台も配備しました。全ての原子炉冷却手段がなくなった場合を想定した注水冷却機能確保対策では、原子炉へ直接注水する配管の設置や大容量ポンプ車6台と消防車2台を配備しています。
井手県議の質問の答弁によると、これらの安全対策に500億円(東海第2発電所と敦賀発電所の2機分を含めて)の費用をかけています。
新安全基準が施行されれば、東海第2発電所に不足する主な設備としては、以下の4点が指摘されています。
- 原子炉格納容器のフィルター付きベント
- 冷却機能を操作する第2制御室
- 難燃性ケーブル
- 新たな津波想定に対応する防潮堤(15メートル級の津波に対応できる防潮堤)
 1月31日の原子力規制委で示された骨子案では、原発の運転を監視する中央制御室が電源喪失や放射性物質による汚染などで使えなくなった場合のために、原子炉格納容器の冷却作業を遠隔操作する「特定安全施設」(=第2制御室など)の設置を義務付けました。また、ヨーロッパの原発ではすでに設置が一般化している、放射性物質をこし取りながら排気し原子炉格納容器の破損を防ぐためのフィルター付きベント(排気)装置を設置すること。原子炉内で使用されている可燃性ケーブルを難燃性の素材に交換することなどが示されています。
1月31日の原子力規制委で示された骨子案では、原発の運転を監視する中央制御室が電源喪失や放射性物質による汚染などで使えなくなった場合のために、原子炉格納容器の冷却作業を遠隔操作する「特定安全施設」(=第2制御室など)の設置を義務付けました。また、ヨーロッパの原発ではすでに設置が一般化している、放射性物質をこし取りながら排気し原子炉格納容器の破損を防ぐためのフィルター付きベント(排気)装置を設置すること。原子炉内で使用されている可燃性ケーブルを難燃性の素材に交換することなどが示されています。
また、今後想定される最大津波に対する防潮堤も懸案となっています。東海第2発電所は福島第1原発事故後間もなく、高さ15メートルで原発の周囲三方を囲む「コ」の字形の防潮堤を設置する計画を立てていましが、新たに提示される津波対策に対応する防潮堤を建設したいとしています。
井手県議は、これらの諸課題を確認した上で、東海第2原発に対して、今後、数百億単位の安全対策のための投資を施し、その負担を国民に総括原価方式の名のもとに強いていいのかと強調しました。
また、昨年8月に成立した改正原子炉等規制法で原発の運転期間が原則40年と規定されてことを踏まえ、こうした安全対策を行った上で、数年しか稼働できなのでは、“廃炉という選択肢もあって良い”との考え方を明らかにします。
(写真は、交流電源喪失時に原子炉を冷却するための電源を供給する電源車を視察する公明党議員団)