住民の避難計画は引き続き検討
3月25日、茨城県の防災会議が開かれ、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて再検討が進められてきた地域防災計画の原子力災害編の見直しを正式に決定しました。
新たな防災計画では、避難などの対策を重点的に実施すべき範囲を原発の半径およそ30kmに拡大し、放射性物質の放出前に避難することになっている半径およそ5km圏の外側では避難や屋内退避について測定した放射線量に応じて判断することなどが盛り込まれました。
原発事故に備えた防災対策を重点的に行う区域「UPZ」(緊急時防護措置準備区域)を、東海第二原発(東海村)から30kmに設定。事故時に即時避難が必要とされる「PAZ」(予防的防護措置準備区域)は、東海原発から5kmとしました。
これまで10キロとされていた重点区域が30キロに拡大し、対象市町村は、東海村、日立、常陸太田、ひたちなか、那珂市の5市村に、水戸、高萩、笠間、常陸大宮、鉾田市、茨城、大洗、城里、大子町を加えた14市町村となり、対象人口は約94万人となり、全国では一番人口が大きくなりました。
避難や屋内退避については、原子炉の状態や災害の規模、空間放射線量に応じた対策を取ります。原子炉を停止・冷却する全機能が喪失した場合、PAZの住民は即時避難することが明記されました。
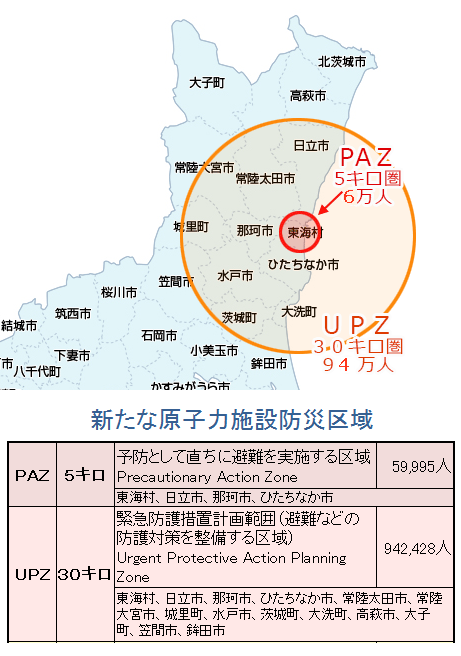
また新たに、住民への広報に関して「携帯端末の緊急速報メール機能など多様なメディアの活用体制の整備に努める」と定めました。有線と無線、地上と衛星など複数のルートを確保し、確実に住民に情報を伝達できるようにします。高齢者や障害者などの災害時要援護者への対応については、県と市町村が、自主防災組織やボランティア団体などと連携し、要援護者の避難誘導体制の強化を目指します。
今回の決定は、国の指針により今年度中に策定が求められてことに対応したもので、大枠が決まっただけです。原子力防災の本丸とも言える、有事の住民避難体制については、今後、市町村ごとにその検討が行われることになります。県は、市町村の避難計画策定を支援することになっており、時間帯や移動させる人数など条件を変えた36パターンで所要時間を推計するシミュレーションを行っています。
しかし、100万人の避難を公共の移動機関が少ない茨城で、どのように確保するのか、所詮は机上の議論であり、実現の可能性はないという声も防災の現場から聞こえます。
具体的で実効性が確保できる避難計画ができない限りは、東海第2発電所は再稼働させない=廃炉、といったドラスティックな選択も必要であると主張します。
安定ヨウ素剤を追加配備
今回の地域防災計画の改定を受け、茨城県は25日、新たにUPZの対象になった地域を対象に甲状腺への被ばくを抑える安定ヨウ素剤を配布しました。
甲状腺への内部被ばくを抑える安定ヨウ素剤は40歳未満の人が対象となり、茨城県での備蓄はこれまでの9市町村14万人分から、14市町村39万3000人分に増えることになります。
国の原子力規制委員会は安定ヨウ素剤について、PAZ(原発から半径5kmより内側)では家庭に事前に配布し、UPZ(5km~30km)では自治体が備蓄して避難の段階で配布することを決めています。
しかし、茨城県は安定ヨウ素剤を服用して副作用があった人への国の補償が十分でないため、現時点では、PAZについても家庭への事前配布は行わないことにしています。
安定ヨウ素剤の服用量と服用量は以下の通りです。
| 対 象 | ヨウ素量 (mg) |
ヨウ化カリウム量 (mg) |
服用方法 |
| 新生児 | 12.5 | 16.3 | 内服液1ml |
| 生後1カ月~3歳 | 25 | 32.5 | 内服液2ml |
| 3歳~7歳 | 38 | 50 | 内服液3ml |
| 7歳~13歳 | 38 | 50 | 丸剤1丸 |
| 13歳~40歳 | 76 | 100 | 丸剤2丸 |
| 40歳以上 | 服用しない | ||
茨城県では原則として、避難所で安定ヨウ素剤を配布し、服用指導を行うことにしています。
日立市では、現在丸剤を70,000丸(31,400人分)、原液を500g(5,300人分)保管しています。対象人口が大幅に増えたことにより、丸剤81,000丸、原液500gを追加備蓄することになりました。丸剤は多賀支所に70,000丸、南部支所に81,000丸を保管します。原液1kgは市保健センターに保管されます。



