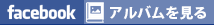高速道路のSA・PAの障がい者スポットにも妊婦さんは駐車OK!
4月6日、NEXCO東日本の常磐道守谷サービスエリア(下り線)で、マタニティマークの普及活動が太田昭宏国交大臣、廣瀨博東日本高速道路代表取締役らが出席して行われました。
NEXCO東日本では、妊婦さんに「安全・安心、快適・便利」に高速道路を利用できるよう、NPO法人ひまわりの会(代表:野田聖子衆議院議員)が中心となって行っているマタニティマークの普及活動や交通安全の啓発活動をサポートし、サービスエリアやパーキングエリアをより使いやすいよう改善を進めています。
サービスエリアやパーキングエリアに設置している高齢者、障がい者等が利用する駐車場は、従来から妊婦さんも利用できる施設ですが、あらためてマタニティマークを掲示することで、妊婦さんに安心して利用できるよう、新たな取組をスタートさせました。
この取り組みの第1弾として、常磐道守谷SAで記念のセレモニーが行われました。
 この日の式典には、太田国交大臣、廣瀬社長、野田衆議院議員を始め、全国統一のマタニティーマークを推進した公明党の松あきら参議院議員、ひまわりの会理事のアグネス・チャンさん、守谷市会田真一市長がら出席しました。また、地元田村けい子県議ら公明党の女性議員も出席しました。
この日の式典には、太田国交大臣、廣瀬社長、野田衆議院議員を始め、全国統一のマタニティーマークを推進した公明党の松あきら参議院議員、ひまわりの会理事のアグネス・チャンさん、守谷市会田真一市長がら出席しました。また、地元田村けい子県議ら公明党の女性議員も出席しました。
ひまわりの会の野田代表から、「高速道路のSAやPAの障がい者用に駐車スポットに、マタニティマークを表示してほしい」との提案を受けて、太田大臣が即断即決でネクスコ東日本など高速道路事業者に依頼。わずか、半月足らずで全国120箇所位上にマタニティーマークが掲示されることが決まりました。太田国交大臣は「国を上げて子育てを支援する姿勢をアピールして行きたい」と語りました。
マタニティマーク:公明党が普及をリード
 マタニティマークの始まりは1999年のことです。女性が妊娠初期であることを周りの人に知ってもらうためにつくった「BABY inME」のマークが最初でした。しかし当時はマタニティマークを扱う地域や団体もさまざまで統一されたものではなかったため、広く普及するには至りませんでした。
マタニティマークの始まりは1999年のことです。女性が妊娠初期であることを周りの人に知ってもらうためにつくった「BABY inME」のマークが最初でした。しかし当時はマタニティマークを扱う地域や団体もさまざまで統一されたものではなかったため、広く普及するには至りませんでした。
マタニティマークが広く知られるようになったのは2006年、厚生労働省が事務局となった「健やか親子21」推進検討会でマタニティマークのデザインが公募により決定された時からです。
2006年3月の参院経済産業委員会と、同4月の参院行政監視委員会で公明党の松あきら副代表が、 通勤電車などで周囲から理解されにくい妊産婦のつらさを訴え、一部の自治体や民間で独自に作製し、好評を得ている妊産婦バッジを紹介。その上で、誰が見ても分かるよう全国統一の基準をつくり、普及を進めるよう主張したのがキッカケとなりました。