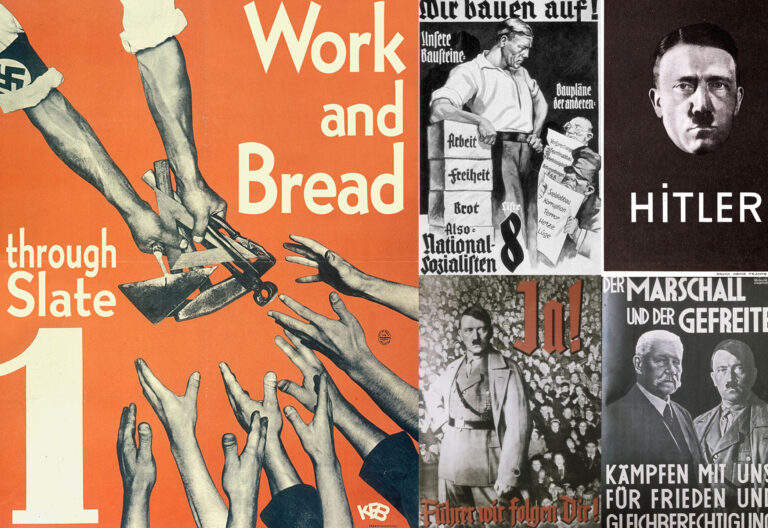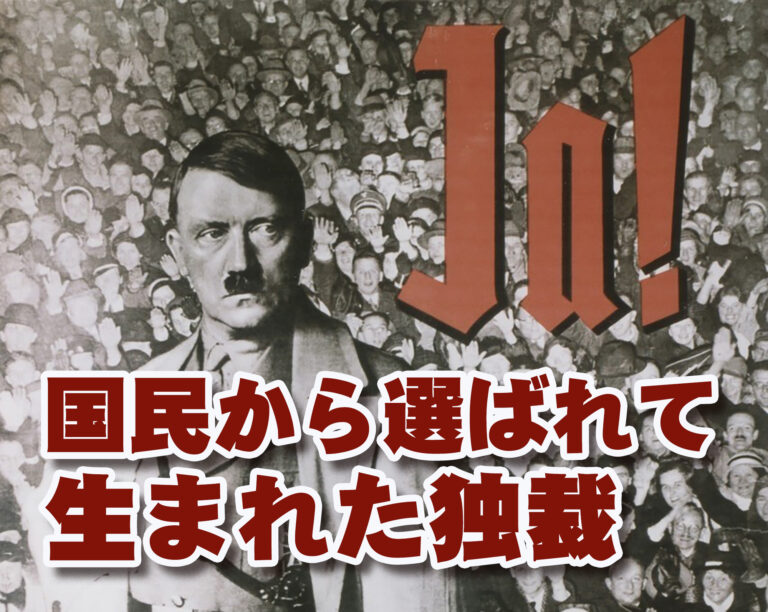安倍政権の主要政策である『地方創生』を具体化する「地方版総合戦略」の策定作業が、各市町村などで佳境を迎えています。
安倍政権の主要政策である『地方創生』を具体化する「地方版総合戦略」の策定作業が、各市町村などで佳境を迎えています。
検討されている自治体の戦略を見ると、地元出身者のUターンや大都市圏からのIターン者に対する支援をはじめ、企業誘致などに重点をおいた内容が目立ちます。雇用の創出が地域の活性化の原動力であり、企業誘致は外せないポイントです。しかし、企業誘致はすべての市町村が狙う戦略であり、それ自体では地方の生き残りレースに勝利することはできません。
もちろん、地方にとって過疎化や人口減少は長年の課題であり、一朝一夕に解決できません。子育て世帯や若者など、さまざまな人々を呼び込む対策に、じっくりと腰を据えて取り組む必要があります。
例えば、都市部では、地方に比べて住居費や生活費などが高く、収入の少ない母子世帯など、生活に苦しいひとり親家庭は少なくありません。
そこに着目した長野県は、ひとり親家庭を対象にした移住支援策を盛り込んだ総合戦略を策定しました。具体的には、ひとり親家庭向けの移住セミナーを開催し、親への就職相談や、家賃が低額な公営住宅・空き家の紹介、保育所の情報提供なども実施しています。ひとり親家庭が県内に移住すれば、生活環境が改善できると同時に、受け入れる自治体側も子育て世代の増加につながるとの判断です。
新潟県長岡市は、若者の移住・定住に焦点を当てた“長岡若返り戦略”を策定しました。戦略には、若者らによる空き家や廃校を利用した集合住宅づくりをはじめ、若者の提案を市政に反映できる「若者会議」の活用などが明記されています。若者が主体的に地元への愛着を持てる政策として注目されています。
地方では、商店やガソリンスタンドなどの閉店により、身近な場所で生活物資が手に入りにくい問題が起きています。買い物支援など、生活の利便性を高める対策も欠かせません。
和歌山県内のある中山間地の北山村では、村営のコンビニエンスストアを開設し、地域の賑わいの拠点としている例もあります。自治体は、こうした事例も踏まえながら、思い切った総合戦略の策定を検討できないでしょうか?
翻って、わがふるさと茨城県、日立市でも野心的な戦略の策定が求められれています。
日立市の山側の団地は、40年前から30年程度前まで盛んに造成され、日立の作業を支えてきた製造業の従業員が多く住んでいます。一つの団地が500戸以上の大型の戸建て住宅地です。いずれも、高齢化が進み、井手よしひろ県議が住む金沢団地(約800戸)の高齢化率は50%を超えています。市街地には急な坂道を使わなくてはならず、高齢者には住みずらい団地となってしまいました。こうした団地群に、買い物の拠点を整備することは人口減少に歯止めをかけるために、必要不可欠な政策です。公営コンビニなどは十分検討に値します。
また、この9月に発生した鬼怒川の大規模水害は、地域創生という視点から、災害対応をもう一度見直す必要性を訴えています。壊滅的な被害を受けた商店街、高齢化した農家を襲った水害。生活を再建する十分な財政的な支援を行わなかったら、被害を受けた市町村の人口現状は加速度的に進んでしまいます。大規模自然災害の復興にどのような支援ができるのか、これは、市町村だけの課題ではなく、国や県も挙げて取り組まなければならない大きな問題です。
どこに住むにしても、暮らしやすさはだれもが求める条件です。きめ細やかな工夫で戦略を前進させ、地方への人の流れを作り出したいと思います。