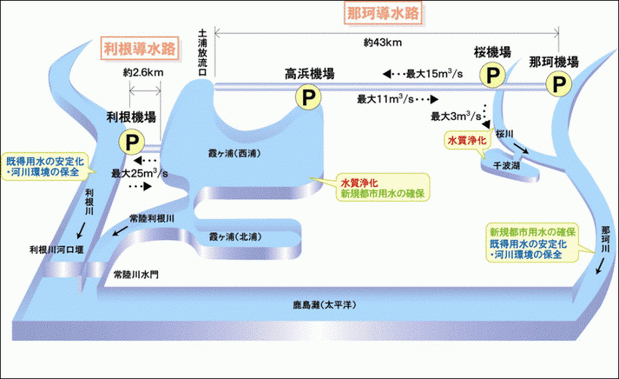
4月27日、霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ「霞ケ浦導水事業」に関して、那珂川流域の茨城県と栃木県の漁協などが国に工事差し止めを求めていた裁判の和解が成立しました。原告の漁協側は、那珂川の生態系に影響が出るなどとして、国を訴えていました。この訴訟は2009年に提訴され、漁協側はアユ漁が盛んな清流の那珂川に霞ケ浦の水が流れ込むため、「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張。一方、国は利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが目的と反論していました。一審の水戸地裁は漁協側の請求を棄却し、国が勝訴していました。
今回、東京高裁(都築政則裁判長)で成立した和解条件では、国と漁業者は工事が完成して本格運用が始まるまで、意見交換の場を毎年、原則一回設けて導水の運用方法を決めるとしています。意見交換する協議会は、今年7月にも第1回が開かれます。
また、生まれたばかりのアユが泳ぐ10月から翌年1月まで4カ月間は、午後6時から午前8時まで14時間、那珂川から取水しないことにしました。霞ケ浦の水を那珂川に流す「逆送水」は、那珂川の環境に影響が出ないよう少量の試験送水をして、水質のモニタリング調査を実施。結果を踏まえて、国が漁業被害の防止策を検討するととしました。
この和解に関して、国土交通省関東地方整備局は「漁業関係者へ丁寧に対応するとともに、関係機関と緊密に連携し、霞ケ浦の水質浄化や、広域で安定的な水利用を図るため、事業を推進する」とのコメントを発表しました。
霞ケ浦導水事業は、那珂川と霞ケ浦間、利根川と霞ケ浦間を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ大規模な事業です。霞ケ浦の水質浄化、那珂川と利根川の渇水対策、茨城県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道・工業用水の供給などが目的です。1984年に国の直轄事業として建設事業着手。総事業費は約1900億円で、茨城県負担額は約851億円。計画変更が繰り返され、当初の完成予定は1993年度でしたが、現在2023年度。予算の約8割を消化したものの、工事の進捗は約4割にとどまっています。国が1984年、工事に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2.6キロ)は完成。那珂導水路(約43キロ)は、30キロ近くが未完成です。民主党政権時代にいったん中断され、自民党政権に戻って継続が決まりました。訴訟に影響もあり、工事は今も再開されていません。



