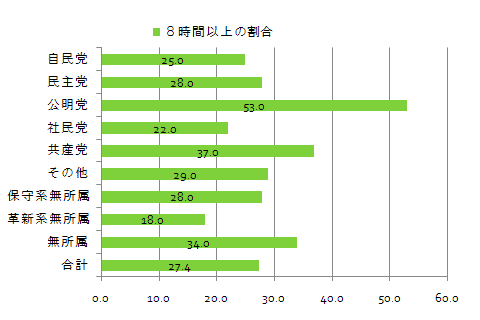去る4月19日、都道府県議会制度研究会が「自治体議会議員の新たな位置付け」と題する報告書を取りまとめました。この報告内容は、後程このブログでも触れたいと思います。ここでは、この報告書がまとめられる過程で行われたアンケートの結果が非常に興味深いのでご紹介します。
このアンケート「全国都道府県議会議員の意識に関する調査報告書」は、都道府県議会議員制度研究会と文科省の21世紀COE「多文化世界における市民意識の動態」プログラムとの共同調査として行われました。
設問の中に、地方議員の役割意識を問う項目がありました。それは「自身が議員活動をするとき関心を払う対象として、『自治体全体』『(自身の)選挙区』『政党(会派を含む)』の3つから優先順位を問う」設問です。
この設問に対して、自治体全体と回答したものが44.6%、選挙区としたものが49.4%、政党としたものが6.0%となりました。都道府県議員は、まさに地域の声の代弁者であるという傾向が強いことがおかがえます。
所属する政党別のクロス集計を見ると、回答に特徴が良く現れます。自民党所属の議員は、選挙区との回答が56.9%に達しています。民主党44.1%、公明党21.7%、社民党34.1%、共産党7.1%などと比べると際だった対称を示しています。
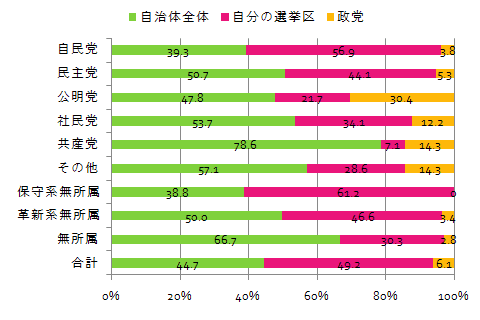
次に、有権者を代表とする方法として、「どちらかといえばできるだけ住民の要求に気を配り、その実現を重視する:代理型」と「住民の利益に関する自己の判断にはある程度自信があるため、それに基づいて決定や行動を行う:信託型」のいずれかを問う設問ありました。
これに対しては、代理型21.2%、やや代理型31.6%、やや信託型30.2%、信託型17.0%と、幾分、代理型とする回答(52.8%)が上回りましたが、信託型(47.2%)との回答とほぼ拮抗しています。所属政党毎のクロス集計を行ってみると、公明党と共産党は8割弱の議員が代理型。自民党と民主党、社民党が半数が信託型という明確な差が出ました。私の初当選以来のモットーは「小さな声を大きく実現」です。有権者の声をしっかりと実現することが政治家のあり方と信じています。まさに、代表型です。
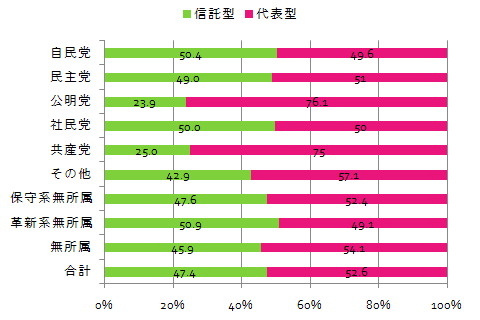
3つめに、議員がどのくらいの時間を議員活動に割いているかを聞いた設問を見てみます。結果は以下のようになりました。
| 2時間未満 | 2~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 | 8時間以上 | |
| 1日の議員 活動時間 | 1.3% | 15.5% | 30.4% | 25.4% | 27.4% |
政党別に見てみると、1日8時間以上議員活動をする割合が、公明党は5割を超えています。共産党が4割弱、自民、民主党は3割以下となっています。公明党、共産党の都道府県議員はほとんど議員専業です。やる気の差もあるかもしれませんが、他の職業をもっているかどうかも大きな差となって現れていると思います。