全国の自殺者は3万3千人で十年連続で3万人台突破
平成19年の全国の自殺者が約3万3000人で、過去二番目に多かったことが、6月19日、警察庁が公表した統計で明らかになりました。 先進国でも日本の自殺率は高く、イギリスやアメリカの二倍以上あります。10年続けて3万人台という、まさに異常事態となっています。
日本の自殺者は長年、2万人から2万5000人台に収まっていました。ところが、1998年に一気に8000人増え、3万人を突破しました。背景には不況やリストラなど、深刻な経済問題があると分析されています。
政府は昨年、自殺総合対策大綱を閣議決定し、自殺率の2割削減を目標に掲げましたが、即効性のある対策は具体化していません。
一方茨城県内の数字をみてみると、自殺者数は815人に上り、記録が残る1983年以降、過去最悪を記録したことがわかりました。他の都道府県と人口10万人当たりの自殺率を比較すると、茨城県は27.5で全国23位でした。
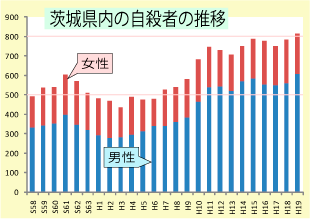 自殺者数815人の内訳は、男性が609人、女性が206人と、全体の4分の3が男性という結果となりました。年代別では、60歳以上が272人と最も多く、50歳代が185人、30歳代が136人となっています。高校生は6人、大学生は9人で、小学生も1人いました。職業別は、無職(年金・雇用保険生活者)が86人や主婦74人などが特徴的になっています。
自殺者数815人の内訳は、男性が609人、女性が206人と、全体の4分の3が男性という結果となりました。年代別では、60歳以上が272人と最も多く、50歳代が185人、30歳代が136人となっています。高校生は6人、大学生は9人で、小学生も1人いました。職業別は、無職(年金・雇用保険生活者)が86人や主婦74人などが特徴的になっています。
自殺の動機のトップは、病気の悩みなどの「健康問題」で357人、全体の43.8%を占めました。2番目は、154人の「経済・生活問題」でした。夫婦関係、親子関係の不和などの「家庭問題」が71人、仕事疲れなどの「勤務問題」は56人と続きました。「孤独感」を理由に自殺した人も10人いました。
井手県議が県警に求めた資料によると、最近問題になっている硫化水素による自殺が、昨年は1件あったことが分りました。今年になってから、すでに5月未までに12件(男10人:女2人)も発生しています。井手県議は材料を簡単に購入できることを問題視しして、対応を県警や関係部署に強く要望しました。
 参考:茨城県内における自殺者の概要(平成19年中)
参考:茨城県内における自殺者の概要(平成19年中)
 参考:平成19年中における自殺の概要資料(全国統計)
参考:平成19年中における自殺の概要資料(全国統計)




男性自殺者数の激増ぶりに対して女性自殺者数は横ばい。この原因は、最近徐々に進められてきた「男女共同参画社会形成」と各家庭の幸福・安定との間のミスマッチが底流にあるのでは? 類型的ですが、以下のような図式を想像しました。
昔なら疎外されていた有能で働く気概のある女性が社会進出→不況時のリストラにより既存システムにあぐらをかいていた中高年男性群の離職→経済苦→失望・自暴自棄
彼らを助けるはずの主婦の社会進出は不十分→主人の維持していた家計を代わりに支えることは期待できない(彼らがそれを望まなかったのか、彼女らが出遅れているのか、状況的に不可能なのか?)
若い時期から社会進出してきた女性は焦って結婚する必要はなく、仮に結婚しても女性の働き続けたい気持ちを理解できない男性もしくはその家族とうまくいかず離婚していく場合も少なくない(彼女らの経済力は疎外された男性を救う方には寄与しない)