地方自治体の退職金の問題がクローズアップされています。団塊の世代が大量に退職時期を迎える中、財政危機にあえぐ自治体は、その対応に苦慮しています。
asahi.com:関西(2004/06/02)翻って、茨城県の状況は以下の通りです。
大阪府、退職手当分割払い検討
団塊世代への支払い控え
財政難の大阪府が、職員の退職手当を分割払いする検討を始めた。高度成長期に大量採用した団塊の世代が退職年齢となり、06年度からは毎年1000億円以上の支給を迫られる。しかも、その時期が財政悪化のピークと重なるのだ。だが、地方公務員法は「一括払い」を原則とする。総務省も「退職者の生活設計にかかわる問題」と慎重な対応を求めている。先行きは不透明だが、府は「背に腹は代えられない」と窮状を訴えている。
市町村レベルでは、大阪府豊中市が今年3月から退職手当の分割払いを始めている。一方、都道府県では「聞いたことがない」(総務省給与能率推進室)という異例の取り組みだ。
府の試算では、定年退職者は03年度1201人だったが、06年度に2485人に跳ね上がり、07年度は3630人、ピークの09年度には4200人を超える。これに伴い、退職手当の支給総額も03年度の最終予算で1010億円を計上。07年度は1371億円、08年度は1404億円になる。
財政悪化のペースも軌を一にする。府は不足する財源を、将来の借金返済のための「減債基金」を取り崩してしのいでいるが、02年度に1000億円以上あった残高は07年度には底をつく。この年度の財源不足額は約5700億円になるという。
府は、退職手当の算定の基礎になる給料月額を、02、03年度と2年連続で計約3%のマイナス改定したほか、03年9月議会で条例改正し、退職手当を約5.5%引き下げた。これに伴い、01年度に約2700万円だった平均支給額は、03年度には約2470万円になったが焼け石に水で、新たな対応を迫られていた。
地方公務員法は、退職手当も含む給与の「全額(一括)払いの原則」を定めている。このため、府は「分割支給に同意した職員に限定すれば、法の趣旨に反しない」と解釈し、同意した職員に限定した分割支給制度を導入する案が有力だ。分割回数などは今後詰める。豊中市の場合、退職した166人中、同意した21人に3回を限度に分割支給している。
団塊の世代への退職手当には、各自治体とも頭を痛めており、02年の朝日新聞の全国調査では、47都道府県と12政令指定市のうち「問題なく支給できる」と回答したのは28だけだった。このため、神奈川県では2年前、有識者による懇話会が、分割払いにも触れた退職手当見直しの意見書をまとめたが、「職員の理解も含め実現は難しい」(人事課)として実現していない。
| 県職員の退職金平均は3100万円。2016年に400億円を突破。 |
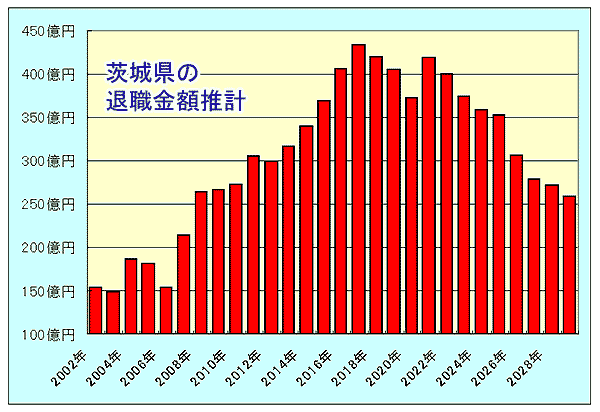
井手よしひろ県議は、2002年1月16日決算特別委員会で、茨城県職員の退職金について取り上げました。
井手県議の質問に対して、平成12年度に定年退職した県職員は596人で、平均退職金は約3100万円、支給総額は約189億7000万円であったことを明らかにしました。
更に井手県議は、今後の退職者の推計と退職金額の推計をただしました。
県人事課の試算によると、定年退職者は2012年度ごろに1000人台を突破し、10年以上にわたって1000人台が続きます。退職者のピークは2016年度の約1400人で、この時の支給総額は400億円以上にのぼる見通しです。
井手県議は、神奈川県が具体的検討を行う機関を設置した例を挙げ、「何らかの抜本的検討に入らないと大変な事態になる」と警告し、次期財政再建プランには検討項目として取り入れることが必要と提案しました。
これに対して、末宗徹郎総務部長も「重要な課題の一つと認識しており、今後十分議論していきたい」と答えました。
<年度ごとの退職者推計と退職金支給金額推計>
| 年号 | 西暦 | 行政職 | 公安職 | 教職 高校 | 教職 小中校 | 合計 | 概算予算 |
| 平成13年 | 2001年 | 124 | 65 | 142 | 164 | 495 | 153億円 |
| 平成14年 | 2002年 | 129 | 64 | 159 | 128 | 480 | 149億円 |
| 平成15年 | 2003年 | 214 | 64 | 137 | 185 | 600 | 186億円 |
| 平成16年 | 2004年 | 201 | 57 | 141 | 184 | 583 | 181億円 |
| 平成17年 | 2005年 | 165 | 76 | 113 | 143 | 497 | 154億円 |
| 平成18年 | 2006年 | 238 | 84 | 154 | 212 | 688 | 213億円 |
| 平成19年 | 2007年 | 247 | 140 | 208 | 256 | 851 | 264億円 |
| 平成20年 | 2008年 | 253 | 118 | 197 | 291 | 859 | 266億円 |
| 平成21年 | 2009年 | 239 | 127 | 186 | 329 | 881 | 273億円 |
| 平成22年 | 2010年 | 292 | 143 | 182 | 368 | 985 | 305億円 |
| 平成23年 | 2011年 | 254 | 132 | 194 | 384 | 964 | 299億円 |
| 平成24年 | 2012年 | 236 | 182 | 185 | 419 | 1022 | 317億円 |
| 平成25年 | 2013年 | 194 | 175 | 176 | 552 | 1097 | 340億円 |
| 平成26年 | 2014年 | 193 | 196 | 192 | 608 | 1189 | 369億円 |
| 平成27年 | 2015年 | 222 | 190 | 216 | 683 | 1311 | 406億円 |
| 平成28年 | 2016年 | 220 | 218 | 216 | 744 | 1398 | 433億円 |
| 平成29年 | 2017年 | 167 | 129 | 214 | 844 | 1354 | 420億円 |
| 平成30年 | 2018年 | 229 | 122 | 179 | 776 | 1306 | 405億円 |
| 平成31年 | 2019年 | 176 | 109 | 212 | 704 | 1201 | 372億円 |
| 平成32年 | 2020年 | 226 | 156 | 256 | 711 | 1349 | 418億円 |
| 平成33年 | 2021年 | 220 | 130 | 279 | 663 | 1292 | 401億円 |
| 平成34年 | 2022年 | 218 | 96 | 291 | 600 | 1205 | 374億円 |
| 平成35年 | 2023年 | 224 | 90 | 239 | 604 | 1157 | 359億円 |
| 平成36年 | 2024年 | 190 | 76 | 261 | 611 | 1138 | 353億円 |
| 平成37年 | 2025年 | 193 | 66 | 223 | 506 | 988 | 306億円 |
| 平成38年 | 2026年 | 185 | 54 | 191 | 468 | 898 | 278億円 |
| 平成39年 | 2027年 | 159 | 51 | 184 | 480 | 874 | 271億円 |
| 平成40年 | 2028年 | 156 | 49 | 193 | 435 | 833 | 258億円 |



