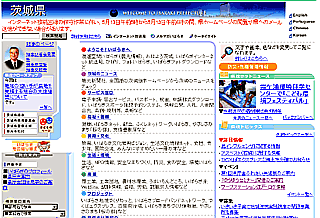 5月11日、茨城県の公式ホームページのリニューアルに当たり、井手よしひろ県議はホームページを管理している広報広聴課長、県民情報センター室長、担当係長らからヒアリング並びに意見交換を行いました。
5月11日、茨城県の公式ホームページのリニューアルに当たり、井手よしひろ県議はホームページを管理している広報広聴課長、県民情報センター室長、担当係長らからヒアリング並びに意見交換を行いました。
茨城県のホームページは、1995年に開設され、99年3月19日以降1882万3145件(2006/5/11現在)のアクセスがありました。国では、2004年に、工業標準化法に基づき、国家規格として「JIS X8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)」により、ウェブコンテンツの情報アクセシビリティを確保するためのガイドラインが定められています。茨城県では、このJIS規格ガイドラインにのっとり、6月をメドに公式ホームページの全面的なリニューアルを予定しています。今日のヒアリング・意見交換では、その方向性と改善案などを話し合いました。
県側からは、以下のポイントでリニュアルにあたることが報告されました。
- ヘッダ・フッタ部のデザインを統一し、県のホームページとしての統一を図ると共に、主なカテゴリーにはどのページからもワンクリックでアクセスできるようにする。
- トップページの中央部に入れ替え可能なイメージ画面を配置し、よりインパクトの強いページづくりをする。
- 注目情報コーナーを設け、緊急、重要な情報をいち早くアクセスできるようにする。
- 分野別の項目から、ワンクリックで目的別の分野にアクセスできるようにする。
- 重要な施策については、バナーを設置しワンクリックでアクセスできるようにする。
- 共通のカテゴリーについては1カ所にまとめて配置し、ユーザビリティの向上を図る。
こうした説明に対し、井手県議は、以下の提案を行い、県側も検討することを確約しました。
2.県のホームページ内の検索機能を充実させること。できればgoogleなどの検索エンジンを活用したシステムを導入すること。トップページにも検索窓を設置すること。
3.検索される機能の強化(SEO対策)すること。
4.スタイルシートを使ったホームページづくりを行い、統一感のあるサイトとすること。
5.A4用紙に最適化した印刷書式を設定すること。
6.RSSによる更新情報の発信の仕組みを導入すること。
7.フレームを使ったページは原則作成しないこと。
2004年6月に、工業標準化法に基づき、国家規格として「JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)」によりウェブコンテンツの情報アクセシビリティを確保するためのガイドラインが定められました。
これを受けて総務省は、2004年11月、「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催。その成果を2005年12月に報告書を公表しました。この報告は「みんなの公共サイト運営モデル 」としてウェブ上にも公開されています。
<参考>みんなの公共サイト運用モデル




まだまだ茨城県のホームページは、詰まらない。
どうせやるなら、他に例のない他の人が見て馬鹿みたい、でも又みたい訪れたいと思う様にしてみたらどうだろうか。
こんな馬鹿馬鹿しくて面白く為になるホームページを作る茨城県は、どういう処だろう一度行ってみたい!
と言うような内容にしてみては。
私は他の人が考えない様なアイデアを、いっぱい持っている、
良かったら手伝いますよ!
まっ!
頭が堅い人や未来を創造できない人、私の考えは馬鹿みたいと思う人は、将来性がない方々である。
長々と拙い文章ですみません。
では、アデオス(^^)v