明確になった公明・伸長と共産・退潮
4月22日、統一選地方選が投開票され、政治の流れは7月の参議院選に向けて大きくシフトしてきました。
統一選の結果をマスコミはどのように評価しているのか改めて確認してみると、「自民退潮」「民主躍進」「公明・共産現状維持」との論調が多くみられました。
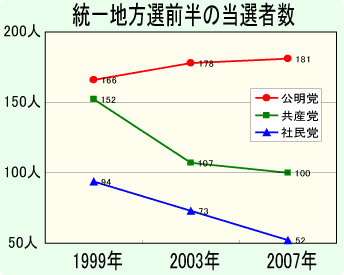 しかし、この報道は的を得ていないのではなかいと思います。例えば、自民退潮との報道には、保守系無所属の存在が加味されていません。例えば茨城県の場合(統一選ではありませんが)、自民党は現有議席44議席を39議席に減らしましたが、その後、無所属で当選した候補全員が自民党入りし、結果的には46議席となり前回を上回りました。全国的にも、自民党の退潮といった結論は簡単には出せない状況があります。
しかし、この報道は的を得ていないのではなかいと思います。例えば、自民退潮との報道には、保守系無所属の存在が加味されていません。例えば茨城県の場合(統一選ではありませんが)、自民党は現有議席44議席を39議席に減らしましたが、その後、無所属で当選した候補全員が自民党入りし、結果的には46議席となり前回を上回りました。全国的にも、自民党の退潮といった結論は簡単には出せない状況があります。
また、公明・共産現状維持との表現にも異議があります。統一選前半戦都道府県・政令措定都市の前々回と前回、そして今回の議席数を比べてみると、公明党:166→178→181、共産党:152→107→100となり、公明党の「2回連続全員当選で議席増」、共産党は「減少傾向に歯止め効かず」という表現が正しいと思います。
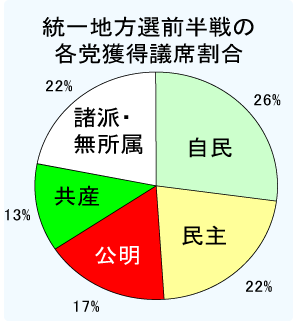 更に、新聞各紙は「地方でも2大政党化」との見出しを打ちましたが、冷静に数字を見てみると、これも誤った世論リードといえます。これも統一地方選前半の結果で見てみると、当選者の党派別内訳は、自民26%、民主21%、公明16%、共産12%、諸派・無所属21%となっています。これをもって、二大政党制と謳うのは無理があります。
更に、新聞各紙は「地方でも2大政党化」との見出しを打ちましたが、冷静に数字を見てみると、これも誤った世論リードといえます。これも統一地方選前半の結果で見てみると、当選者の党派別内訳は、自民26%、民主21%、公明16%、共産12%、諸派・無所属21%となっています。これをもって、二大政党制と謳うのは無理があります。
住民の生活に直結した地方政治の場では、有権者の選択は多様であり、むしろ多党化や脱政党化が進んでいるという方が正しい分析の結論であると思います。



