苦情のトップは架空請求、手口は巧妙化
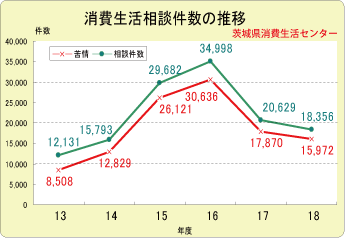 茨城県消費生活センターの平成18年度相談状況がまとまり、公表されました。
茨城県消費生活センターの平成18年度相談状況がまとまり、公表されました。
それによると、相談件数は平成17年度より2,273件減少して18,356件(対前年度比11.0%減)になり、平成16年度をピークに2年連続で前年度を下回わりました。このうち苦情相談は前年度より1,898件減少して15,972件(対前年度比10.6%減)となりました。
苦情相談の主な商品・サービスを見てみると、商品・サービスが特定できない商品一般が、4,697件で前年度の約1.4倍となり、前年度に引き続き第1位でした。このうち4,382件、(構成比93.3%)は商品内容が不明な債務の返済を請求されたという、いわゆる架空請求の相談でした。
第2位は、フリーローン・サラ金の相談でした。前年度より74件増加して2,234件となりました。複数の金融機関から多額の借金をして返済が困難になる多重債務の相談が多くなっています。債務整理の他に消費者金融会社への利息の過払金返還訴訟やグレーゾーン金利見直しの報道に合わせ、金利の見直しに関する相談も寄せられています。その他には、ヤミ金融、保証金詐欺などに関する相談が寄せられています。
第3位は、電話情報提供サービスで、前年度より半減して1,465件となり、相談件数減少の最大の要因になりました。身に覚えのない有料サイト利用料を請求されたという、いわゆる架空請求の相談は前年度より672件減少して258件になりました。なお、携帯電話やパソコンを使用して有料サイトに接続し、高額な登録料や利用料を請求された相談が、引き続き多く寄せられています。
相談件数が全体では減少した一方、自動車の購入後の不具合・故障トラブルやキャンセル料に関する相談、賃貸アパート等の退去時の原状回復費用負担や敷金返還に関する相談が引き続き多く寄せられています。
他には、個人事業主を中心に高額な電話機のリース契約に関する相談や、過去に契約した複合サービス会員権や資格取得用教材を引き合いに業者が新たな契約を迫る、いわゆる「二次被害」の相談、高齢者を中心に高額な健康食品の相談も多く寄せられています。
架空請求の相談は、前年度より15件減少したものの4,748件と横ばいでした。請求内容は,商品不明な未納代金の訴訟を取下げる相談を受けるとして連絡を求めるものが9割以上を占め、差出人名も法律関係行政機関に似た名称をかたるなど、巧妙化しています。
 参考:茨城県消費生活センターのHP
参考:茨城県消費生活センターのHP



