茨城県では、今年10月1日からインターネット公開も含めた統合型GISの運用を開始することになりました。GISとは、地理情報システム(Geographic Information System)の英語の頭文字で、地理的位置情報を基本に、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。
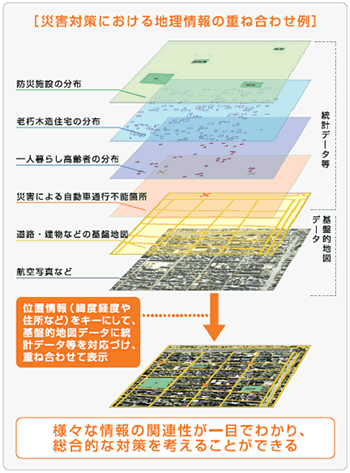 統合型GISは、県や市町村の業務で取り扱っている地理情報をデジタル化・共用化し、相互利用を可能とする横断的なシステムです。地理情報の重複整備を防ぎ、庁内他課や市町村との情報共有を図ることができる他、多様な地図データの重ね合わせによる各種情報の一元的な把握・分析による政策形成等、行政事務の効率化・高度化を図ることが可能となります。
統合型GISは、県や市町村の業務で取り扱っている地理情報をデジタル化・共用化し、相互利用を可能とする横断的なシステムです。地理情報の重複整備を防ぎ、庁内他課や市町村との情報共有を図ることができる他、多様な地図データの重ね合わせによる各種情報の一元的な把握・分析による政策形成等、行政事務の効率化・高度化を図ることが可能となります。
また、県民・企業等に対しては、地図情報としての行政情報の発信や情報共有のためのツールを提供することによって、コミュニティや産業活動の活性化等にも活用できます。
茨城県の統合型GISの整備費用は1億1700万円。年間運用経費は3550万円(5年間で,1億7800万円)。整備費と5年間分の運用経費2億9400万円を県と茨城県内44市町村が2分の1ずつ負担します。
統合型GISの整備効果は、年間2億2190万円の行政事務経費(地図の作成・加工等の作業時間の短縮、位置情報を伴う問い合わせ対応時間の短縮、地図関係印刷物作成費の削減等、システムの利活用)を削減することが出来ると試算されています。県における効果が5490万円/年、市町村における効果が合計で1億6700万円/年とされています。
さらに、茨城県では国内でも希な市町村との共同開発を実現したため、市町村単独整備の場合と比較して割勘効果により、約10分の1に導入経費を圧縮することが出来ました。また、航空写真撮影費が、作業効率の向上や共通経費の削減等により、個別に撮影するより約4分の1の費用で済むようになります。
統合型GISは県庁と市町村の内部LAN(イントラネット)とインターネットで提供されます。9月上旬から県及び市町村職員によるテスト運用を行います。10月1日から本格運用を開始します。年度内には、県下すべての航空写真情報なども撮影・掲載し利活用できるようにします。
 参考:国土交通省のGISホームページ
参考:国土交通省のGISホームページ
 参考:GISの新たな可能性(日経BP)
参考:GISの新たな可能性(日経BP)
(1)整備費:1億1700万円
(システム設計費、システム開発費、機器設定費、初期搭載データ整備費)
(2)年間運用費:3550万円(5年間で1億7800万円)
(システム運用保守費、機器リース費、更新地図搭載費)
(3)県と市町村の費用分担について
整備費及び5年間の運用費の総額(2億9400万円)を2分の1ずつ負担する。
(県:1億4700万円、市町村:1億4700万円)
●整備効果の試算
(1)統合型GISの利活用による効果
地図の作成・加工等の作業時間の短縮、位置情報を伴う問い合わせ対応時間の短縮、地図関係印刷物作成費の削減等、システムの利活用による効果として、以下のとおり試算している。
・県における効果:5490万円/年
・市町村における効果:1億6700万円/年(全市町村合計)
(2)県市町村共同整備による効果
・システム整備・運用費の削減:割勘効果により、市町村単独整備の場合と比較して約10分の1に(総務省試算:今回のシステム整備費を1市町村当たりに換算すると130万円の整備費が必要)
・航空写真撮影費の削減:作業効率の向上や共通経費の削減等により、整備単価が約4分の1に(単独撮影の場合:約9万円/k㎡ →共同撮影の場合:約2.4万円/k㎡)
・自治体間の情報共有の円滑化や県民等への行政界を超えた広域的な情報提供の実現となる
ベースとなるデータには地形をありのままに写しとった空中写真データ、植生や気象などを表す人工衛星データ、道路や河川などの台帳データ、都市計画図や土地利用図などの主題図(地図)データ、人口や農業などの統計データ、固定資産や顧客リストなどの各種データベースなど多様な種類があります。
GISはこうした位置・空間データと、それを加工・分析・表示するためのGISソフトウェアから構成されます。GISソフトウェアで様々なデータを電子地図の上に層(レイヤ)ごとに分けて載せ、位置をキーにして多くの情報を結びつけます。これにより、相互の位置関係の把握、データ検索と表示、データ間の関連性の分析などが可能になります。
そのため、GISは非常に幅広い用途に使われています。たとえば、道路、水道、電気、ガスなどの社会インフラを管理しているのもGISですし、土地・建物の不動産情報や施工管理、店舗の出店計画や顧客管理などのエリアマーケティング、災害時を想定した防災計画にもGISが使われています。
上の図は災害対策においてGISを利用した例です。上の1枚1枚が特定のデータを持ったレイヤで、こうした複数のレイヤを位置情報をキーとして重ね合わせていくことで、情報の関連性が一目でわかるようになります。この結果から、総合的な災害対策を考えることができるわけです。
また、GISはインターネットでの地図情報表示や、GPS(全地球測位システム)を利用した携帯電話のナビゲーションシステムにも役立っています。
(国土交通省のGISホームページより引用しました)



