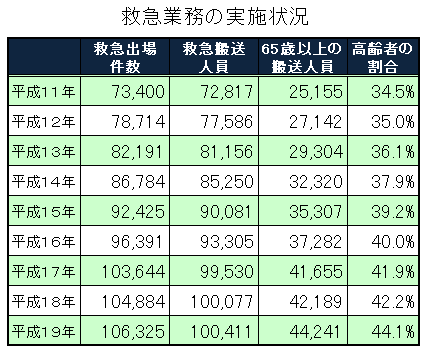9月9日は「救急の日」。井手よしひろ県議は、県消防防災課から、昨年一年間の救急の状況を聴き取りしました。
平成19年の救急搬送人数は、10万411人で、前年を334人上回り過去最高を更新しました。搬送人数は平成11年に7万2817人でしたが、平成13年には8万人を超え、平成18年には10万人の大台を突破しました。昨年は、99年の1.38倍に達しました。
搬送した患者の高齢化が顕著で、平成11年に65歳以上のお年寄りの割合が34.5%であったのに対し、平成19年には44.1%と1割近くも増加しています。
また、患者を医療機関に収容するまでの所要時間も、年々長くなる傾向にあります。昨年は、平均7.8分で前年より1.1分遅くなりました。さらに出動要請から医療機関に収容されるまでの時間は37.2分と、2.8分も遅くなりました。医師不足による救急病院の受け入れ体制の不備が最大の要因です。
搬送理由の内訳は①急病:58.4%、②交通事故:17.0%、③一般負傷:11.7%などとなっています。搬送者のうち軽症者が51.8%と過半数に達し、大きな問題となっています。
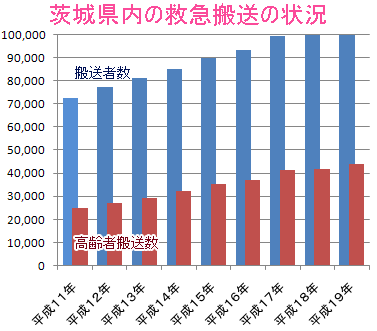 また、応急措置が施された急病患者とそうでない場合の救命率の比較も公開されました。
また、応急措置が施された急病患者とそうでない場合の救命率の比較も公開されました。
県内の救急隊が搬送した心肺停止の患者2573人のうち、救急現場に居合わせた家族などにより応急措置が施された患者は366人(14.2%)で、その患者の1ヶ月生存者数は32人で生存率は8.7%でした。応急措置が実施されなかったり、発見が遅れて応急措置が行われた患者は2207人、その1ヶ月生存者数は95人、生存率4.3%でした。応急措置が行われた場合の生存率が2倍以上になっているとの説明がありました。