より大きな地図で 茨城県内の高速道路無料化(H22年度) を表示
2月2日、国土交通省は「平成22年度高速道路無料化社会実験計画(案)」を公表しました。
流通コストの引き下げを通じた生活コストの引き下げや、産地と消費地へ商品を運びやすくするなどによる地域と経済の活性化を目的として、民主党はそのマニフェストに高速道路の原則無料化を掲げました。平成22年度は、社会実験を通じて影響を確認しながら、平成23年度より段階的に無料化を実施するとしています。
無料化の社会実験を行う区間は、約6000億円必要とした全国実施の予算が1000億円に縮減されてことから、6月から全国の高速道路37路線の50区間、計1626キロで無料化の社会実験を開始します。
実際に選定された路線は、一部を除いて“盲腸路線”ともいえる建設途中の路線か、末端部の路線がほとんどで、1000億円者巨費を投じて、どれだけ経済効果が発揮できるか大変疑問な路線が目立ちます。
さらに、地元自治体との調整が全く行われていないため、混乱を起こすケースも少なからずあると思われます。
特に茨城県内唯一の実験となった「東水戸道路」ひたちなかIC~水戸南IC間10キロ区間は、県の常陸那珂有料道路との整合性が大きな問題となります。常陸那珂有料道路は、ひたちなかIC(東水戸道路と直結)からひたち海浜公園ICに至る延長約2.9kmの自動車専用道路です。地域高規格道路水戸外環状道路の一部で、茨城県道57号常陸那珂港南線に指定されており、茨城県道路公社が一般有料道路として管理しています。したがって、常磐道友部ジャンクションから国営ひたち海浜公園方向に通行すると、北関東道区間(~水戸南IC)は有料=東水戸道路区間(水戸南IC~ひたちなかIC)は無料化=常陸那珂有料道路(ひたちなかIC~ひたち海浜公園IC)は有料という、大変複雑な料金体系になる可能性があります。今後、県の有料道路に関しては、その対応が検討されることになりますが、常識的に言えば、地元自治体(道路管理者)との協議を経て実験区間を決定するのが道理ではないでしょうか?
民主党政権のいう政治主導とは、地方無視の独裁政治と言わざるを得ません。

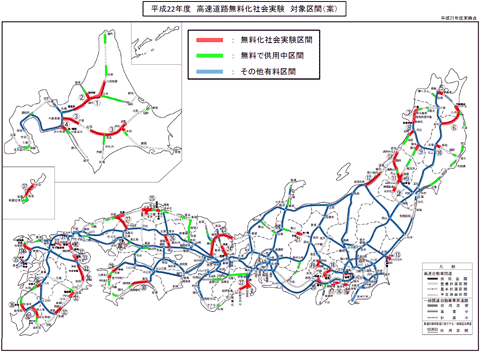
 参考:
参考:

