 昨年12月の県議選を契機に、茨城県議会では議会改革への具体的な動きが顕在化しています。
昨年12月の県議選を契機に、茨城県議会では議会改革への具体的な動きが顕在化しています。
2月28日の定例県議会の初日、議会最大会派のいばらき自民党より次回の議会運営委員会(3月3日開催予定)で、一般質問の質問枠拡大について具体的な提案をするとの発言がありました。
正式な提案の前にいばらき自民党から打診された内容は、現行の年間30人を40人に増やすことが骨子となっています。現在、午後1時から1日3人ずつ10日間、県議会の一般質問は行われています。本会議の開会日を増やさずに、質問枠を拡大するのは、午前中に1枠増やすことが一番容易であり、経費の拡大や執行部を過度に拘束することにもならないために、現実的な提案だと理解しています。
ただし、現状の質問時間を確保するのは最低限の条件であり、代表質問80分(自民120分、民主、自民県政、公明80分)、一般質問60分の質問時間は確保すべきだと意見を述べました。
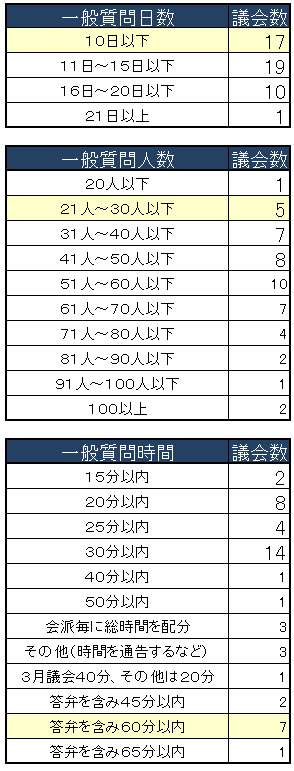 他県議会の一般質問の状況を議会事務局の調査で見てみると、年間の質問日数は10日以下が17、11日~15日が19、16日~20日が10、21日以上が1となっています。
他県議会の一般質問の状況を議会事務局の調査で見てみると、年間の質問日数は10日以下が17、11日~15日が19、16日~20日が10、21日以上が1となっています。
年間の質問者数は、20人以下が1、21人~30人が5、31人~40人7、41人~50人8、51人~60人10、61人~70人7、71人~80人4、81人~90人2、91人~100人1、100以上は2となっています。
また質問時間は、15分以内が2、20分以内8、25分以内4、30分以内14、40分以内1、50分以内1、会派毎に総時間を配分3、その他(時間を通告するなど)3、(3月議会40分、その他は20分)1、答弁を含み45分以内2、答弁を含み60分以内7、答弁を含み65分以内1となっています。
確かに、こうした他県の事例を眺めてみると、茨城県の質問回数、人数などが少ないことが目立ちます。たとえ、40人に拡大しても、平均以下と言うことになります。
ただし、茨城県議会の特異性も考慮しなくてはいけません。現在の茨城県議会の各会別の議席数は、いばらき自民党45議席、民主党6議席、公明党4議席、自民県政クラブ4議席、みんなの党2議席、共産党1議席、無所属3です。
つまり質問回数を40回以上に増やしても、それ以降増えるのは自民党の質問回数だけだということです。一会派が突出して議席を持っている議会においては、質問回数を増やすことが議会の活性化に直結しないと言うこともあることを留意する必要があります。


