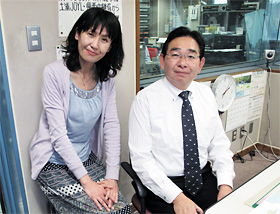 5月11日、井手よしひろ県議は県議会公明党を代表して、地元ラジオ局茨城放送に生放送に出演。東日本大震災から丸2カ月経た茨城県内の状況や課題について語りました。以下、出演時の原稿をご紹介します。
5月11日、井手よしひろ県議は県議会公明党を代表して、地元ラジオ局茨城放送に生放送に出演。東日本大震災から丸2カ月経た茨城県内の状況や課題について語りました。以下、出演時の原稿をご紹介します。
(パーソナリティ:渡辺美奈子さん)『がんばろう茨城 復興に向けて・・・!』。この時間では今週一週間、東日本大震災の被災地である茨城県内を奔走している、茨城県議会に議席を有する各政党の担当者に、発生から2カ月、復興の現状や被災者の生活再建の状況、郷土の再生に懸ける思いなどを伺っております。
きょうは、公明党茨城県本部幹事長の井手よしひろ県議会議員に話を聞きます。よろしくお願いします。
(井手よしひろ県議)こんにちは公明党の井手よしひろです。よろしくお願いします。
(渡辺)さて2ヶ月を振り返り、どこまで復興できたのか、復興の足取りをどう見ますか。
(井手)去る3月11日に発生したマグニチュード9.0の「東日本大震災」は、大津波と相まって東北・関東地方に想像を絶する被害をもたらしました。
この度の災害により亡くなられた多数の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様にお見舞いを申し上げます。
2カ月経って、県民生活は落ち着きを取り戻していますが、未だに400人を超える方が、家に戻ることが出来ず避難所で生活をされています。
繰り返す余震や、安定しない福島第一原発の状況は、県民の復興への足並みに、大きな障害となっています。
そして、なにより、復興をリードする国の対応が全く見えていません。復興の大前提である、第一補正予算が成立するまでに2カ月近く掛かってしまいました。本格的な復興の枠組みやその予算は、夏以降になるといわれています。
私は、一人の現場の地方議員として、菅直人総理のリーダーシップの欠如に、歯がゆい思い、怒りさえ感じています。
(渡辺)原発事故の風評被害が続くなどしています。残された課題をどう考えますか。
(井手)現時点で、震災復興への最大の障害は、原発問題です。なによりも、その早期対応を東電と政府に求めたいと思います。
その上で、風評被害への賠償としっかりした対応が求められます。
先月末、茨城県のJAグループは、出荷規制や風評被害の賠償請求の第一弾として14億円を東電に請求しました。この額は、茨城農業や漁業が、被った被害のごく一部であると認識しています。国は賠償基準を明確に示すべきです。そうしないと、全国トップクラスの茨城の農林水産業がダメになってしまいます。
政府は、原発事故の風評被害は保証すると、繰り返し返し言っているのですから、現実に一刻も早く、仮払いなど具体的な措置を行うべきです。
(渡辺)公的支援についてはどう考えますか。
(井手)良く今回の大震災は、1000年に一度の震災であるとか、想定外の大地震であるとかいわれます。もし、それが本当ならば、政府の対応も今までの延長線上の公的支援であっては、ならないと強く申し上げたいと思います。
私は、公明党の幹事長として、この2カ月に県内の地元日立市をはじめとして、県内20市町村を現地調査し、被災した方や農業者、漁業者、中小企業の経営者など、様々な方からお話を聞いてまいりました。
現行の枠組みでは、被災者への支援策として、
亡くなった方に「災害弔慰金」が世帯主に500万円、その他の方に250万円。重い障害が残った方には「災害障害見舞金」として最大250万円。おやごさんを亡くした子どもに「あしなが育成会一時金」が最大40万円支払われます。
家屋の損害には、被害の応じて最大300万円の「被災者生活再建支援金」が支払われます。
また、日赤や県からの義援金として亡くなった方や全壊の住宅に50万円が配られます。
しかし、例えば、地震や津波で全壊した家を解体するだけでも100万円近い費用を請求されたという事例もあり、とても生活の再建には足りません。
また、潮来市の日の出地区など鹿行地域で顕著な、液状化被害にも、国はあらたな基準を作り、生活再建支援法が適用できるようにすると言っていますが、家を補修するのであれば、その支給額は最大200万円しかありません。液状化で傾いた家を正常にするためには、500万円以上の費用が掛かると言われ、生活を建て直すにはあまりにも少なすぎます。
今回のような広大な範囲の震災被害は前例がなく、茨城県は茨城県の、福島県は福島県の、宮城県や岩手県はその地域にあった公的支援の枠組みを作る必要があります。その意味では、県ごとに災害復興基金を国が数兆円規模で醸成し、地域のニーズにあった支援策を行うことを提案したいと思います。
(渡辺)茨城は今後、何を目指すべきでしょうか。
(井手)茨城県が被った産業被害は甚大です。道路や、港湾、公共施設や病院など、県民の生活基盤の復興も急がれます。教育や文化、スポーツ、芸術に関する施設にも大きな影響がありました。
こうした様々な課題を一挙に解決することは、予算の面からも資材や人材の制限もあり、到底無理があります。
何を一番先に復興させるか、次にどれに予算を投入されるか、復興への明確な青写真を描く必要があります。県民生活と茨城の産業を復活させるために、県民の知恵を糾合して、”生活大県いばらき・復興プロジェクト”のような総合的な計画を大至急立案する必要があると思います。
緩慢な政府の対応に対して、今回の大震災に対する、民間の対応は際立っていました。
私は、地震直後、県の災害本部で一昼夜、不眠不休で地震の情報収集などにあたりました。
県の災害拠点病院の非常用電源が、燃料不足で無くなってしまうと言うときに、駆けつけてくれたのは、民間のガソリンスタンドの経営者の皆さんでした。
茨城県は、自らが被災県であると言う側面と、より被害が深刻な東北三県への支援の最前線という二重の性格を持っていると思います。
茨城発のあらたな試みとして、民間のバス会社と県の社会福祉協議会のコラボによって、ボランティア・バスが宮城県の被災地に運航されています。私もゴールデンウィークに石巻でのバスボラに参加しました。
被災地の復興にボランティは不可欠ですが、個人で参加するのは負担が重すぎたり、現地のニーズと参加するボランティアのニーズが合致しないなど効率的な支援が出来ません。その点、団体バスを活用したバスボラは、あらたな被災地支援の仕組みとして、今大いに注目されています。
その先駆的な仕組みを茨城のバス会社が挑戦してくれたことは、大きな意味合いがあると思います。
行政も他のバス会社も、こうした新しい流れをより支援していくことが望まれます。
16年前の阪神淡路大震災で、日本には”ボランティア”という言葉が定着しました。
この東日本大震災では、国や地方自治体が行う公的支援=公助と個人の努力による自助、そして地域社会やNPO・ボランティアによる共助のバランスの取れた地域福祉、地域防災の仕組みを確立して行かなくてはならないと思いますし、このピンチこそ最大のチャンスでもあります。
(渡辺)今日は、ありがとうございました。
(井手)ありがとうございました。




日立市豊浦地区
豊浦台団地の被災状況は深刻です
でも多くが年金生活者であり
震災保険も加入していません
子や孫が融資して建て替えさせたくとも
その予算はありません
また引き取りたくても生活に余裕のない事もあります
豊浦台団地の田尻団地松が丘団地の視察をお願いします