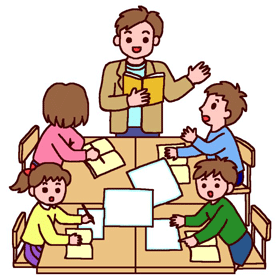 8月5日、茨城県内の教育者の方々と懇談する機会を持ちました。約2時間にわたり、茨城県の教育界の課題や改善点など忌憚ない意見交換が出来ました。県議会公明党からは、井手よしひろ県議の他、田村佳子県議、八島功男県議が参加しました。
8月5日、茨城県内の教育者の方々と懇談する機会を持ちました。約2時間にわたり、茨城県の教育界の課題や改善点など忌憚ない意見交換が出来ました。県議会公明党からは、井手よしひろ県議の他、田村佳子県議、八島功男県議が参加しました。
この懇談会の中で、特に話題となったのが管理職登用の茨城県の独自の取り組みと専科教諭の採用拡大の問題でした。
茨城県では、校長や教頭などの管理職登用の条件として、小学校・中学校をそれぞれ6年間、経験しなくてはならないという独特の仕組みがあります。確かに、教員の資質向上のためには、小学校と中学校の両方を経験することは大きなメリットになると思われます。しかし、その両方を経験しなくてはならいないことが、管理職になる条件でないと考えられます。「小学校教諭として求められる資質」と「中学校教諭として求められる資質」は、大いに異なると思うとの意見が多数寄せられました。
茨城県では、「資質を向上させるため」として、ほぼ強制的に小学校と中学校を経験させる人事異動が実施されています。他の都道府県で同様のことをしている自治体はほとんどありません。「希望者」が異動できるシステムは有効であると思われますが、希望していない教師にとっては大変な負担となっています。「中学校で長く勤めた先生が、管理職になるために小学校に異動した。中学校ではバリバリであったが、小学校では児童の実態が中学生に比べてあまりに違う。言語もなかなか通じない。はっきり言って、ぐちゃぐちゃの1年間であった。これでは、この教師に1年間担任された児童は被害者といえませんか?」との、厳しい意見も上がりました。
また、管理職登用試験に関する受験回数や年齢による制限も話題となりました。茨城県では、教頭試験は3回、(53歳まで)、校長試験は2回(55歳まで)という、受験回数制限、年齢制限が内規としてあります。年齢制限は、より希望の持てる年齢に、回数制限は撤廃すべきとの声が寄せられました。
さらに、専科教員の拡充に対する要望を出されました。専科教員とは、原則として学級担任がすべての教科を担当している小学校において、理科・書写・体育・図画工作・音楽・家庭など、主に実技教科を専門的に担任する教員を指します。特に高学年においては専門的な教材研究や技能の実施(実験、ピアノ演奏など)が必要で、学級担任の負担が大きいため配置されています。教育委員会において学校の規模別に加配人数が決められています。しかし、小規模校では配置できないことがあるため、教頭や教務主任が専科を引き受けたり、交換授業によって複数学級の同一教科を一人の教員が負担するようになっています。子どもたちの情操を育てるためにも、小学校の低学年にも採用することも検討すべきとの意見がありました。



