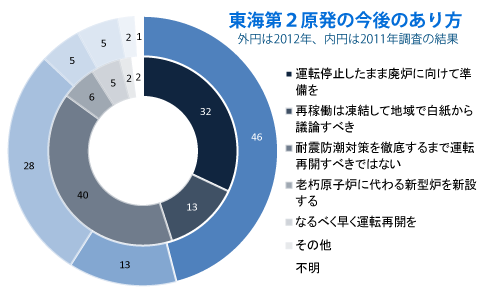
9月1日、茨城大学地域総合研究所(茨大地総研)は、東海第二原発の将来などについて調査したアンケートの結果を公開しました。
茨大地総研は、JCO臨界事故10年目となった2009年度から日本学術振興会より科学研究費の交付を受け、「臨界事故10年を経た東海村の防災システムと地域再生の総合的研究」を開始し、2010年度には東海村、日立市、那珂市、ひたちなか市各地域住民を対象に、「地域社会と原子力に関するアンケート」を実施しました。福島第一原発事故後に実施した2011年度のアンケート調査では、地域社会と原子力の関係についての一般的な設問に加え、「原子力事故と情報」に焦点を当て設問を追加し、震災に伴う原発事故が茨城県内の原発立地地域周辺住民に与えた影響を考察しました。
今回の調査では、震災・福島原発事故から1年以上を経過した段階で福島原発事故の影響がどのように変化し、東海第二原発の再稼働問題についての意識や原発問題全般についての意識がどのように変化したのかに焦点を当ててアンケートを実施しました。
調査対象は、原発立地自治体である東海村に加え、隣接する日立市南部(多賀支所・南部支所管内)、那珂市、ひたちなか市の住民のうち、20歳以上65歳未満の有権者、各1000名、合計4000名を各地域の選挙人名簿から無作為に抽出。調査票は郵送配布し、自書方式で郵送で回収しました。調査票有効回収数は全体で1109通、有効回収率は27.7%でした。
東海第二原発の今後のあり方を問うた質問では、「運転停止したまま廃炉に向けて準備を」が46%(昨年32%)と過半数に迫りトップに。二番目は「耐震防潮対策を徹底するまで運転再開すべきではない」という慎重論が28%(昨年40%)。「再稼働は凍結して地域で白紙から議論すべき」との意見が13%(昨年13%)が三番目で、再稼動に慎重な意見は85%から87%に増加しました。
また、全国の原発のあり方について問うた質問には、「現状よりも減らすべきだ」が最多で35%、「原発はゼロにすべきだ」が33%と、この二つを合わせると68%が「減原発」志向となっています。
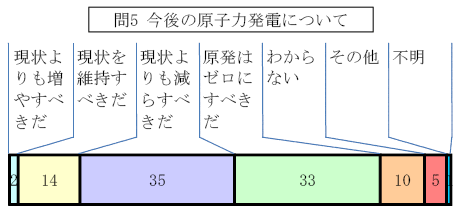

 参考:「
参考:「


続き
■夢のプルサーマル発電は、ウソでした。内閣府の調査により、使用済み燃料の処理に困った末の方便と判明
核燃料サイクルは、フィクションだ。それゆえに、原発関係者はフィクションを演じてきた。政府が「脱原発」を宣言すれば、こうした構図が崩れる。
◆「ウラン節約」ウソだった 再処理「原発維持のため」 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012090502000123.html
■覚えていますか?「六ヶ所村の覚書」。核燃料サイクルが破綻した時、全国の原発に使用済み核燃料を返還する、爆弾条項の事を…
「再処理前の一時貯蔵」という名目で受け入れ。もんじゅ廃炉にして再処理技術開発を停止すると、再処理前の一時貯蔵ではなくなる。「最終処分場」は契約外だから、拒否は当たり前。
◆アングル:政府のエネ政策が土壇場で難航、核燃サイクル地元が反発[ロイター 2012/09/10] http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE88904M20120910?sp=true
◆英仏、返還廃棄物受け入れ要請 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2012/20120913085457.asp
返答ありがとうございます。よくわかりました。
ただ、自分は防潮堤を作る事には賛成です。それは、再稼働のためではなく、使用済み燃料が当分の間その原発にあり続けるからです。もって行く先が無いからです。
浜岡原発2号機は廃炉が決まっていますが、まだ使用済み燃料がプールにあるため、耐震補強することになりました。
■《原発は倫理的なエネルギーではない》
▽最終処分の困難さ ▽事故の影響は、国境を超える ▽事故の影響と処理は、次の世代まで続く
■決定を下したのは、ビジネス至上主義の政治的決定
科学や技術は、人間に様々な可能性を与えてくれるが、これらの可能性は、人間を如何なる方向へも導くことが出来る。『私達が進むべき道を決める基準は、科学でも技術でもなく、道徳であるべき』。
■もう逃げ場無し。核燃料プールがいつ満杯になるか計算してみたら、12年以上運転できるのはたったの3基だった。再処理工場(青森県六ケ所村)の貯蔵プールも、既に97%以上が埋まっている
▽12年の意味…むつ市の例から、中間貯蔵施設を新設するのに要する期間
◆核燃料プール 数年で満杯 6割が運転不可に
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/images/PK2012090402100020_size0.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012090402000109.html
■アメリカは、使用済み燃料の貯蔵規則を見直す(=最終処分場の指針見直し)まで、原発の新設や運転期間の延長は認めない方向へ。
最終処分場が存在しないのに、使用済み核燃料が累積していくのは、誰が見てもおかしい。
アメリカは、使用済み核燃料の最終処理の問題に解決の見込みがないから、脱原発に大きく舵を切る方向へ。
◆原発の新設認可せず=核燃料の貯蔵規則見直しまで-米規制委[2012/08/08] http://www.jiji.com/jc/c?g=int&k=2012080800646
読者様
更に付言すれば、現在、日本げんでんは東海第2発電所に、15メートル級の津波にも耐えられる防潮堤を建設する計画を持っています。
その費用は100億円の単位になると言われています。
いくら金を掛けても、電気料に上乗せすれば良い。何としても再稼動させたい。との思いからです。
稼動後34年経った東海第2発電所にとって、これだけの費用を掛けて再稼動させる経済的な意味も、再検討する必要があると、私は考えています。
読者様
もう一点指摘させていただければ、もっと現実的な選択なのですが。防潮堤の嵩上げに掛かった費用は、電気料に上乗せすれば良いという発想もあることは否定できません。
安全対策に掛かった費用は、“総括原価方式”という仕組みの中で、最終的には電気料に上乗せされて、利用者=国民が負担します。極論を言えば、安全を確保し、その費用は国民が負担してくれるのですから、防潮堤をつくっても日本げんでんは、痛くも痒くもないのです。
県が進めた方が良いという安全対策を、積極的にげんでんが行った背景は、ここにあるとも言えます。
読者様へのご質問にお答えします。
直接アドレスが記載されていませんので、ブログ上での回答となります。
結論から言って、私は茨城県と日本げんでんのコミュニケーションの深さだと思います。
原子の灯が最初に点った茨城県は、単に原発立地の金銭的効果のみならず、その技術や安全性を日本中に広める使命感をもって、原子力事業者と行政が対峙してきました。
日本げんでんは、東電のような電力事業者とは一線を画す、地域との共存共栄という姿勢を感じています。事故以来、私たち公明党は東海第2発電所の再稼動に慎重(反対)の姿勢を鮮明にしていますが、原電の対応は今までと全く変わらず、げんでんの責任者が足繁く様々な説明に来て下さいます。どの政党よりも早く、国会議員の原発現地調査を受け入れてくれました。
こうした姿勢の違いが、県の津波想定に基づいた防潮堤の嵩上げを、積極的に認めたのだと推測しています。
以下に書いた原発への独自対策は、どういう経緯で行なわれたのでしょうか?どこの党が、議会で取り上げたのでしょうか?
福島県など他の県では、電力会社からの金欲しさからか、原発の独自対策が出来ていませんでした。なぜ、茨城県では出来たのかを知ることは重要だと思います。
対策が終わったのが、震災2日前の3/9。その対策があっても、東海第二は危機一髪でした。特に、対策してなかったら、福島と同じでメルトダウンし、関東は全て終わっていたでしょうから。
調べてみて下さい。
◆[AERA 2012/07/16号]
2002年7月、政府の地震研究推進本部(地震本部)が福島第一の沖を含む日本海溝沿いでM8.2前後の地震が起きると発表。しかし、中央防災会議は、2006年の被害予測で、この予測を切り捨て。
茨城県は、中央防災会議が切り捨てた地震本部の予測についても、2007年、独自の被害想定をし、それに従い、東海第二原発は、東日本大震災の2日前までに、津波に対する補強工事を終え、メルトダウンから逃れている。