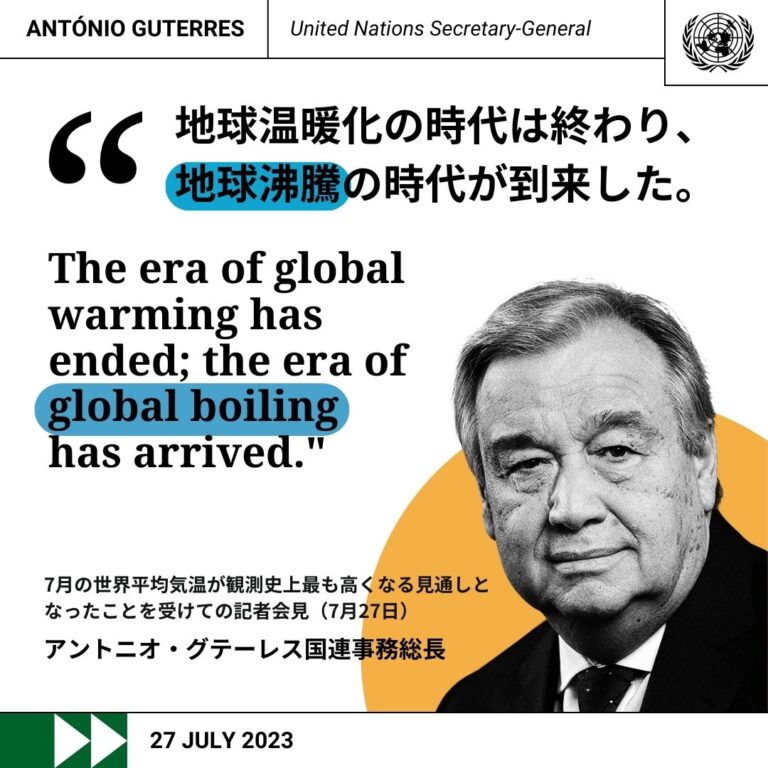私は昨年に引き続き、今年も守谷市市民大学にて「SDGsとまちおこし」をテーマに講座を担当させていただきます。この講座をきっかけに、守谷市の行政施策をSDGsの視点から改めて評価し、私なりに整理してみました。以下、その概要をご紹介します。
守谷市は、つくばエクスプレスの開通を契機に人口が急増し、若い世代や子育て世帯が多く住む都市として発展してきました。市はこの変化に柔軟に対応し、保育施設の整備や保育士支援策の充実、ひとり親家庭への支援など、子育て環境の整備に注力しています。これにより、「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念に沿った、安心して子育てができるまちを実現しています。
教育分野でも、「きらめきプロジェクト」などに象徴される一貫教育体制の構築や、小中学校における週3日5時間授業の導入など、全国でも先進的な取り組みが見られます。ICT教育、教科担任制、英語教育の強化、不登校対策、キャリア教育の推進など、すべての子どもに質の高い学びを届けようとする守谷市の姿勢は、SDGs目標4(質の高い教育をみんなに)を体現しています。
さらに、障がい者支援やまちづくり、市民参加、環境対策にも広く力を注いでいます。都市基盤の整備とともに、住民主体の「まちづくり協議会」が市内各地に根付きつつあり、行政と住民が一体となって地域課題を解決する協働の仕組みが整っています。
環境面では「ゼロカーボンシティ」宣言に基づく脱炭素政策、ごみ削減への取り組み、地域の自然資源を生かした環境学習など、SDGsの環境目標にも着実に取り組んでいます。最近では不用品リユースの仕組みを民間と連携して導入するなど、創意工夫のある施策も注目されます。

ただし、課題もあります。再生可能エネルギーの導入規模は十分とは言えず、地域による開発格差や市民活動への参加率の低下も懸念されています。また、行政のデジタル化や防災対策では、他市と比べて遅れが見られる点もあります。特に、気候変動リスクや高齢化への備えが求められる今、すべての世代・地域を巻き込んだ“誰ひとり取り残さない”共創のまちづくりが、より重要になっています。
守谷市は、コンパクトながら質の高い行政と市民力を兼ね備えた自治体です。その姿勢は、持続可能な地域づくりの好事例として他地域の参考にもなり得ます。これからも、守谷市の歩みを通じて、地方からのSDGs実践のヒントを皆さまと共有していければと思います。