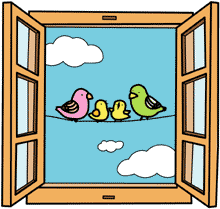 日本国憲法制定から58年目の朝を迎えた今年の5月3日。国会の憲法調査会の議論も取りまとめられ、憲法改正が現実のものとして取り上げられはじめた実感があります。
日本国憲法制定から58年目の朝を迎えた今年の5月3日。国会の憲法調査会の議論も取りまとめられ、憲法改正が現実のものとして取り上げられはじめた実感があります。
憲法制定以来の58年間で、時代は大きく動き、国民生活の質も、経済活動の規模も、政治文化の様相も様変わりしました。東西の壁の消滅と米国の「9・11」に代表される国際社会の環境は、まさに劇的に変化しました。
「変わる世界と日本」を見据えながら、憲法論議をどう実りあるものに集約させていくか、日本人は大きな歴史の分岐点に立っているのかも知れません。より冷静で、より真摯な未来志向の論議が政党と政治家に求められています。「改憲か」、「護憲か」で不毛の政治的対立を繰り返すことは、愚かなことです。
憲法調査会の報告書で、特に重視したいのは、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の憲法三原則について、「これを維持すべき」との考えで一致している点です。
憲法を取り巻く環境は大きく変わりましたが、この三原則は、より深く広く国民意識に定着してきました。三原則にNoを唱える人は、皆無に等しいのではないでしょうか。
また、現憲法は、世界中からもその先進性が評価されていることも見逃せません。
この二点を考え合わせると、憲法論議は全文を残すことを前提に、「何が不足しており」「何を付け足すか」を考えて方がよいことに気付きます。これが、公明党が提唱する「加憲」の手法です。
例えば、三原則のうちの平和主義に対して、「国際協力のために九条を改正すべきだ」といった議論があります。しかし、これが詭弁であることは、現に展開されているPKOの例を見るだけで十分です。それでも国際協力を明文化するのであれば、9条を堅持したまま、新たにそれを書き加えればよいのです。加憲の手法は、「対決型」「強行型」の憲法論議を「調和型」「合意型」のそれへと転換する効果も期待できます。
憲法調査会の議論がまとまった今、何にもまして重要なのが、国民的議論の高まりです。
個人としての市民の「参加」なくして、憲法は空文化してしまいます。今の憲法はこのままでよいのか、変えるとするならば、どのように変えるのか、58回目の憲法記念日をきっかけにじっくりと考えてみたいものです。
現行憲法は維持しつつ、そこに新しい条文を書き加え、補強していく「加憲」方式は、以下のような理由から、極めて現実的な方法。
第1に、現行憲法は優れた憲法であり、それが広く国民の間に定着し、積極的に評価されているという基本認識があります。
第2に、諸外国を見たとき、時代状況に合わせて憲法を補強していくというスタンスをとる国が少なくないからです。アメリカは、従来の条項をそのまま置いた上で修正条項を加えていく「アメンドメント方式」をとっていますし、フランスの憲法においては1789年の「人権宣言」が今も有効とされています。
第3に、憲法改正について規定した憲法96条第2項では、「(憲法改正について国民の承認を経たときは)天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」という条文があり、この「一体を成すもの」という表現にはアメリカ式の「加憲」のニュアンスが出ています。事実、96条の「改正」の英訳は「アメンドメント」という英語が充てられていますし、「日本国憲法は、本来的にアメリカ的なアメンドメント方式、つまり増加型改正が基本になっている」(江橋崇・法政大学教授)との指摘もあります。



