 8月30日、井手よしひろ県議ら公明党県議団(代表足立寛作県議、田村けい子県議が参加)は、笠間市内の茨城県動物指導センターを訪問しました。この視察には、日立市内のアニマルセラピーのボランティア代表も参加しました。
8月30日、井手よしひろ県議ら公明党県議団(代表足立寛作県議、田村けい子県議が参加)は、笠間市内の茨城県動物指導センターを訪問しました。この視察には、日立市内のアニマルセラピーのボランティア代表も参加しました。
動物指導センターは、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」などに基づいた業務を行っています。昭和62年より業務の効率化を図るため、全県下の動物行政を一元化し、「人と動物の共生する地域社会の実現」を目指して、動物愛護精神と適正飼養の普及啓発に努めています。
県内で2006年度、県動物指導センターに引き取られたイヌの頭数は7728頭。その内捕獲されたものが5928頭、引き取られたものが1800頭に上りました。飼い主に返されたり(133頭)、新しい飼い主に譲渡とされたもの(256頭)はごくわずかで、7339頭が処分されました。
 茨城県のイヌ・ネコの処分数は、毎年減っているものの全国最多(05年度)で、システムの見直しや飼い主のモラル向上への取り組みが望まれています。動物指導センターでは、市町村を専用車両で巡回し犬猫の「定時定点回収」を実施していますが、「処分数が多いのは回収のせいだ」との批判もあり、2003年度に111カ所あった回収地点を、本年度42カ所まで減らしました。また、2004年10月からは、それまで無料だった引き取り(飼い主がイヌ・ネコの処分を目的にセンターに持ち込むこと)を有料化しています。
茨城県のイヌ・ネコの処分数は、毎年減っているものの全国最多(05年度)で、システムの見直しや飼い主のモラル向上への取り組みが望まれています。動物指導センターでは、市町村を専用車両で巡回し犬猫の「定時定点回収」を実施していますが、「処分数が多いのは回収のせいだ」との批判もあり、2003年度に111カ所あった回収地点を、本年度42カ所まで減らしました。また、2004年10月からは、それまで無料だった引き取り(飼い主がイヌ・ネコの処分を目的にセンターに持ち込むこと)を有料化しています。
保護期間(センターに収容されてから処分されるまでの期間)を、1979年度から、狂犬病予防法が定める2日間を2日延長し、収容から5日目以降に犬の処分を行っています。2001年度からは迷い犬の情報をネットで公開し、迷いイヌなどの発見に便宜を図っています。
井手県議らは、庄司昭センター長などから現状と課題について説明を聴取し、意見交換を行いました。●処分期間を5日目以降から7日目以降に延長できないか、●現状の施設を愛護・啓発関連施設と処分施設に分けられないか、●イヌの鑑札のデザインを一新するなど付けてもらえるものに変更してはどうか、●マイクロチップの普及を図るべきだ、●NPOやボランティアとの連携をもっと強化すべきではないか、などの意見が公明党側から出されました。
こうした視察の結果などを踏まえ、9月議会では田村県議が一般質問で、住民とペットとの共生について県執行部の認識を質す予定です。
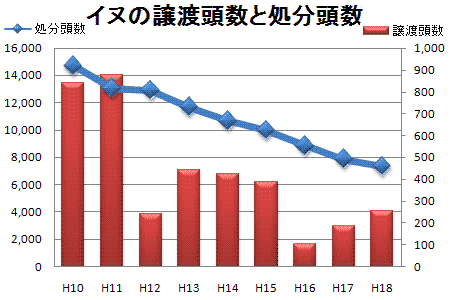
 参考:茨城県動物指導センターのHP
参考:茨城県動物指導センターのHP




たくさんの犬猫が処分されていると聞き、先日猫の譲渡に関して茨城県動物指導センターに電話しました。なぜ犬の譲渡は行っているのに猫の譲渡ないのですか?どんな病気を持っているかわからないのは犬も猫も同じでは?猫の譲渡情報バンクは設置されてはおりましたが件数が少ない上に手続きに時間が必要で担当の方の対応もあまり感じが良くありませんでした。いまのままでは茨城県の犬猫の処分数は減らないのでは?他県から茨城県に5年前に転居しましたが、茨城県の犬猫の処分数最多には驚きました。が、確かに弱いものの命を軽視している人が多いのは感じます。県民のモラルが低すぎます。
ブログ読ませて頂きました。動物の処分というのは、
茨城がワーストというのは有名だと聞かされた事がありました。これはとても恥ずかしい事です。
子供がいる家で動物に仔が生まれて親がそれを捨てるのを見て育つ子供は、命は捨ててもいいんだ と勘違いをします。
何とか即処分ではなく、おとなしく安全そうな犬などでしたら、里親を捜すなどの方法を取ることなど、できたら 少しでも良い方向に、更に学校などでも命の大切さは人間だけではなく、すべての命をいつくしむ
心がもっと伝わったら本当にうれしいと 思います。
少しずつでも改善がされる事を願ってやみません。