運輸・郵送部門で水戸市は、CO2の排出量全国ワースト1
地球温暖化対策の強化が叫ばれる中、中長期視点で二酸化炭素などの温室効果ガスを大幅に削減するためには、「まちづくり」を考えることが重要です。環境省ではこうした観点から、平成17年10月から今年(平成19年)3月まで「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会」を11回にわたり開催してきました。
その報告書「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会 ~環境にやさしく快適に暮らせるまちを目指して~」は、非常に興味深い内容になっています。
それによると、、日本のCO2排出量の増加は自動車走行量や床面積などの「活動量」が増えたことが原因としています。特に都市部では機能が拡散しているため、一人当たりの運輸旅客部門のCO2排出量が多く、また就業者一人当たりの床面積が広い傾向にあります。このため、都市計画や交通政策に地球温暖化対策の視点を盛り込み、公共交通を軸とした拠点集中型の地域・都市構造の構築を図ることが、中長期的な温室効果ガスの排出量削減には不可欠だとしています。
具体的には、生活が車に依存する地方都市の方が、電車やバスなどの公共交通機関が充実した都市部よりもCO2の排出が多いと分析されています。
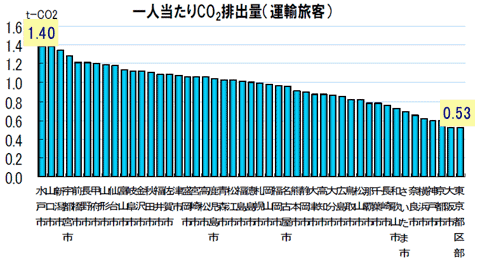
上のグラフは、国立環境研究所「市町村における運輸部門温室効果ガス排出量推計手法の開発および要因分析」より作成されたもので、運輸部門でのCO2排出量は日本国内でも地域によって差があり、人口100万人以上の都市は少ない傾向がみられ、最も少ない東京23区と最も多い茨城県の水戸市とでは2.7倍の差があります。人口数十万人の都市はばらつきがみられ、やや少ない松山市とやや多い山形市とでは約1.5倍の差があります(数値は1999年当時のものです)。
そして、同報告書では、地球温暖化対策の観点からのまちづくりに向けて、以下の具体的な提案を行っています。
- 都市の二酸化炭素削減目標や交通機関の分担率目標を設定する等、都市計画や交通政策に地球温暖化対策の視点を盛り込む。
- 今後の人口減少・高齢化社会を踏まえると、都市構造の再編は必須であり、その手段として、市街化区域の適切な設定、固定資産税・住民税の税率を撤退すべき地域には高く、再結集を図るべき地域には低く設定する「固定資産税・住民税のグリーン化」などのインセンティブを与える仕組みを構築する。
- 無秩序な郊外開発を抑制し、運輸旅客・民生業務部門の活動量による増加基調を食い止める。また、駅周辺に商業施設、住宅等を再結集するなど、LRT等の公共交通を軸とした拠点集中型の地域・都市構造を構築して、二酸化炭素排出量の大幅削減を図る。
- 誘発交通を十分考慮し、「渋滞解消のための道路整備」から「自動車交通需要の抑制」を図る。
- 自動車利用者が負担すべき「環境損傷」「空間損傷」4などの社会的費用等を踏まえ、「歩行者・自転車、LRT、大規模緑地、風の道等」のための道路空間の整備、公共交通機関への支援、自転車利用の促進を図る。
- 大規模集客施設の利用客による二酸化炭素排出量の把握の仕組みを構築する。
- 緑の容積率等の指標により定量的に評価する仕組み、分析のための高解像度のシミュレーションシステムの開発、税による消費者の選好誘導等の施策を通じた魅力的な環境街区の設計、モデル的な街区の構築、ストック化を進める。
- 環境負荷を始めとする社会的費用を反映する仕組み(開発権取引、空間損傷等に対する費用負担としての税制等)の構築を図る。
- 「環境とまちづくり」に関する情報の提供・普及啓発、専門的知見を持つ人材の育成・活用を図りながら、住民参加型のまちづくりを行っていく。
 参考:「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会 ~環境にやさしく快適に暮らせるまちを目指して~」
参考:「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会 ~環境にやさしく快適に暮らせるまちを目指して~」



