11月6日、県議会決算特別委員会が開催され、井手よしひろ県議は、「高額医療・高額介護合算制度」の具体的な申請方法について、県の対応を質問しました。
公明党の主張が認められ実現した「高額医療・高額介護合算制度」の申請が、この8月1日からスタートしました。
社会保障の柱である医療保険と介護保険はそれぞれ、費用が高額になった場合に、利用者負担を軽減するため、自己負担に限度額(1カ月当たり)が定められています。しかし、制度は異なっても負担するのは同じ家計。それぞれ限度額が設定されているとはいえ、両方を合算(=合計)した場合、家計を圧迫する高額な負担となるケースがあります。
このため、公明党は高齢社会を見据え、医療保険と介護保険をまたいで横断的に負担を軽減する仕組みの創設を強力に推進してきました。こうした要望を受けて、2003年3月28日に閣議決定された医療保険制度の抜本改革に関する基本方針には、医療保険と介護保険の「自己負担の合算額が著しく高額になる場合の負担の軽減を図る仕組みを設ける」ことが明記されました。これが具体化されたものが、「高額医療・高額介護合算制度」です。
「高額医療・高額介護合算制度」は、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年間の基準額を超えた場合に、その超えた分が利用者に払い戻され仕組みとなっています。
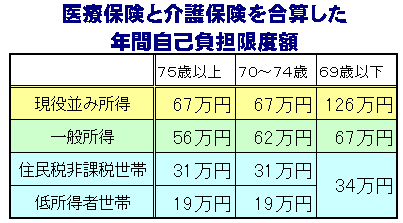 例えば、夫婦とも75歳以上(住民税非課税)で、夫が病院に入院して自己負担が30万円、妻が特別養護老人ホームに入所して自己負担が30万円だったとすると、従来は世帯で60万円の負担ですが、合算制度における基準額が31万円のため、29万円が払い戻されることになり、大幅に負担が軽減されます。
例えば、夫婦とも75歳以上(住民税非課税)で、夫が病院に入院して自己負担が30万円、妻が特別養護老人ホームに入所して自己負担が30万円だったとすると、従来は世帯で60万円の負担ですが、合算制度における基準額が31万円のため、29万円が払い戻されることになり、大幅に負担が軽減されます。
基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。また、今年度は経過措置として、08年4月1日から09年7月末日までの16カ月分の自己負担が対象となり、基準額は4カ月分を加えた額に設定されています。
具体的申請は、医療保険、介護保険の両方の負担額が確定しないとできません。現在、茨城県においては国保連(県国民健康保険連合会)がその合算額を集計しており、11月中には市町村に通知されることになっています。市町村では、各世帯別の所得を勘案して、合算制度に該当する世帯には12月中に申請用紙を郵送することになっています。
申請用紙が届いた世帯は、必要事項を記載して市町村窓口に申請をすれば、合算限度額以上に支払った保険料が戻ってくることになります。
井手県議は、11月6日の決算特別委員会で、県民への告知を広く行うべきと要望しました。
医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」



